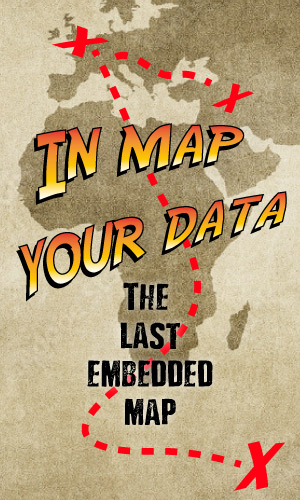Search
死刑制度合憲判決事件

死刑制度合憲判決事件(しけいせいどごうけんはんけつじけん)とは、1946年(昭和21年)9月16日未明に広島県佐伯郡吉和村(現:広島県廿日市市吉和)で発生した尊属殺人・殺人・死体遺棄事件。
刑事裁判では、日本国憲法施行後の日本における死刑制度の存在は違憲であるか、合憲であるかが争われた(違憲審査)。最高裁判所大法廷は1948年(昭和23年)3月12日、死刑制度は憲法第36条で禁止された「残虐な刑罰」には該当せず、合憲であるとして被告人側の上告を棄却し、死刑を確定させる判決を言い渡した。以降はこの判例における憲法解釈が死刑制度存置の根拠とされ、日本の裁判所はこの判例に従って死刑判決を宣告してきたとされている。
事件
犯人である男Mは1927年(昭和2年)1月10日生まれ(事件当時19歳8か月・少年死刑囚)。事件現場は犯人Mの自宅で、その所在地および被告人Mの本籍地は広島県佐伯郡吉和村字妙音寺原2228番地。
Mは尋常小学校4年生の時に父親と死別して以降、家が貧しかったことから居村の「教龍寺」へ奉公に出された。さらに荒物屋の丁稚・料理店の板場・自動車会社の助手などの仕事を転々としていたが、最後の自動車会社で会社の金を費消したために解雇され、1946年(昭和21年)2月ごろに生家へ帰ってきた。当時、生家では母A(当時49歳)と妹B(当時16歳)がそれぞれ手内職・日稼ぎなどをして、乏しい配給生活で糊口を凌いでいたが、もともと板場のような職業に興味を持っていたMは田舎での労働を好まず、自分の力で一家を支えようとする意気込みもなかったため、一家はMの帰宅によりさらに暮らしにくくなった。また、Mは食欲旺盛なため、食生活もより一層逼迫したことから、母A・妹Bから邪魔者扱いされ、家庭内は険悪になっていた。
同年6月ごろ、Mは自宅がそれまで融通を受けていた近所の「住田精米所」から米2斗を盗み出し、大部分を煙草などと交換したことが発覚して検挙された。同事件は起訴猶予処分となったが、それ以来はこれを苦にしたAから口癖のように「お前があんなことをしたから世間に恥ずかしいし、『住田精米所』から米を借りることもできなくなった」と愚痴を言われ、冷遇されるようになったため、同年9月13日 - 14日ごろには「母Aと妹Bを殺してしまおうか」という気持ちになっていた。
Mは9月15日(事件前日)、友人宅へ遊びに行ったが、17時30分ごろに帰宅すると2人は既に夕食を済ませており、食物は全く残っていなかった。そして、Bから「仕事もせずに遊んでいる者は飯を食べなくてもよい」と放言されたことに腹を立て、再び家を出てから23時ごろに帰った。その際にはいつもと異なり、AやBが自分のための床を敷いていなかったため、Mは一時は床で寝たが、空腹や立腹のあまり寝付けず、夕方の2人からの仕打ちや、日ごろの冷たい態度を思ううちに「もう2人を殺そう」と決断した。そして翌日(9月16日)1時ごろ、自宅納屋から藁打ち槌(重さ一貫匁余り)を持ち出し、熟睡していたA・Bを相次いで撲殺。2人の死体を自宅東南方数間の地点にあった古井戸内に投げ込んで遺棄した。
Mは事件後、近所づきあいがあった近隣住民の男性(友人)甲に対し、「2人は山県郡の親族の家に行っている」と話していたが、甲は2人が祭りや正月にさえ姿を見せないことを不審に思い、事件翌年の1947年(昭和22年)1月17日に別の友人(乙)とともにM宅を訪れた。甲と乙から「2人(AとB)を探さずにいては申し訳ないのではないか」と問い詰められたMは黙り込んでいたが、2人が帰るときにM宅の畑の中にある井戸の蓋をどけ、中を覗いてみたところ、被害者2人 (A・B) の死体が発見された。そして乙が駐在所に事件を届け出、被告人Mは刑法199条(殺人罪)および刑法200条(尊属殺人罪)および死体遺棄罪で起訴された。
刑事裁判
本事件の刑事裁判は、旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)に基づいて行われた。
被告人Mに対する5月23日に第一審の公判は広島地方裁判所刑事第1部(横山裁判長)で開かれ、1947年(昭和22年)5月16日の公判でMは大町検事から死刑を求刑された。同年5月23日にMは広島地裁で無期懲役の第一審判決を宣告された、同年8月25日、広島高等裁判所で死刑の控訴審判決を宣告された。弁護人の西村直人は憲法違反などを理由に最高裁判所へ上告し、弁護人は上告趣意書で「死刑は最も残虐な刑罰であるから、日本国憲法第36条によって禁じられている公務員による拷問や残虐刑の禁止に抵触している。そもそも『残虐な殺人』と『人道的な殺人』とが存在するというのであれば、かえって生命の尊厳を損ねる。時代に依存した相対的基準を導入して『残虐』を語るべきではない」として、死刑適用の違憲性を主張した。このため、本事件については死刑制度が憲法36条に違反するか否かについて憲法解釈が行われることになった。
「残虐な刑罰」の定義については、本判決以降の最高裁大法廷判決(1948年6月23日宣告・刑集2巻7号777頁)にて「不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰」とされているが、学説上は「刑罰の種類・性質が残虐である場合」「犯罪と刑罰が極端に均衡を失している場合」が問題とされる。そのため、前者の観点からは「死刑そのものは残虐な刑罰に該当するか」「死刑の執行方法(絞首刑)は残虐と言えるか」がそれぞれ問題となり、後者の観点からは「軽微な犯罪に対して死刑を予定・選択することが残虐と言えるか」が問題とされた。
大法廷判決
最高裁判所裁判官11人による最高裁大法廷(塚崎直義裁判長)は、1948年(昭和23年)3月12日に「日本国憲法の主旨と死刑制度の存在は矛盾せず、合憲である」として、被告人Mの上告を棄却する判決を言い渡した。これにより、被告人Mの死刑が確定した。
判決文では「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。……憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に……もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。」として、「社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている」と結論付けた。
次いで「残虐な刑罰」と主張した点については、「刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。」としている。
なお、この判決には島保・藤田八郎・岩松三郎・河村又介の4裁判官による補充意見と、井上登裁判官の意見が付せられている。
- 島裁判官ら4人の補充意見は、「ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は国民感情によつて定まる問題である。而して国民感情は、時代とともに変遷することを免かれないのであるから、ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが、後の時代に反対に判断されることも在りうることである。したがつて、国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。かかる場合には、憲法第31条の解釈もおのずから制限されて、死刑は残虐な刑罰として憲法に違反するものとして、排除されることもあろう。しかし、今日はまだこのような時期に達したものとはいうことができない。」としている。
- 井上裁判官の意見は、島裁判官らの補充意見は「何と云つても死刑はいやなものに相違ない、一日も早くこんなものを必要としない時代が来ればいい」といったような思想ないし感情が基になっているのであろうと推察した上で、「この感情に於て私も決して人後に落ちるとは思はない、しかし憲法は絶対に死刑を許さぬ趣旨ではないと云う丈けで固より死刑の存置を命じて居るものでないことは勿論だから若し死刑を必要としない、若しくは国民全体の感情が死刑を忍び得ないと云う様な時が来れば国会は進んで死刑の条文を廃止するであろうし又条文は残つて居ても事実上裁判官が死刑を選択しないであろう、今でも誰れも好んで死刑を言渡すものはないのが実状だから。」とする。
大法廷判決後
本判決以降、2018年(平成30年)時点までに日本の裁判所は死刑の合憲性・違憲性について、新たな判断を示していない。なお、1993年(平成5年)9月21日には最高裁第三小法廷(園部逸夫裁判長)にて言い渡された保険金殺人事件(強盗殺人、死体遺棄、殺人、詐欺被告事件)の上告審判決(控訴審の死刑判決に対する被告人側の上告を棄却)の補足意見で、大野正男裁判官が「本判決(大法廷判決)から45年が経過し、その間に死刑制度とその運用に著しい変化がある。しかし、死刑に対する国民の意識・感情について(各種世論調査などの結果を踏まえ)検討すると、我が国民の多くは、今日まで死刑制度の存置を希望してきており、死刑廃止を基本的に支持する者の中でも、即時全面廃止を支持する者は少なく、その多くは死刑の漸次的廃止を支持しているとみられる」と指摘した。その上で、大野は「死刑適用の一般的基準については『各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合』と判示されている。このように、裁判所は死刑を極めて限定的にしか適用していないが、なおその厳格な基準によっても死刑の言渡しをせざるを得ない少数の事件が存在しているというのが我が国の現状である。」と指摘し、「我が国民の死刑に対する意識にみられる社会一般の寛容性の基準及び我が国裁判所の死刑の制限的適用の現状を考えるならば、今日の時点において死刑を罪刑の均衡を失した過剰な刑罰であって憲法に反すると断ずるには至らず、その存廃及び改善の方法は立法府にゆだね、裁判所としては、前記のように死刑を厳格な基準の下に、誠にやむを得ない場合にのみ限定的に適用していくのが適当である」と結論づけている。
1949年(昭和24年)7月27日、福岡刑務所で死刑囚Mと同日(1948年3月12日)に死刑が確定した死刑囚の刑(絞首刑)が執行された(当時の法務大臣:殖田俊吉)。
反応・評価
この大法廷判決は死刑およびその執行方法(絞首刑)の合憲性を肯定した判例として、2019年(令和元年)時点でもなお重要な判例とされている。永山則夫連続射殺事件における上告審判決(1983年7月8日・第二小法廷判決 / 死刑選択基準「永山基準」を明示)などでもこの判例が踏襲されている。一方、大法廷判決当時は本事件に関する社会的関心は低く、日本国民の死刑に対する関心は一般犯罪よりも、むしろ戦争犯罪の方に向いていた。
弁護士の六車明は2018年に「井上裁判官は本判決で、『一日も早くこんなもの(死刑制度)を必要としなくなる時代が来ればいい』と述べたが、それから70年が経過した今日の日本でもなお、死刑制度を支持する世論は根強い。これは、大法廷判決当時の国内情勢(GHQ占領下の戦後復興期)から70年が経過してもなお、4人の裁判官が指摘したような『公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代』には至っていないということではないか。その理由としては、日本社会が経済優先を本質とする社会だったことも挙げられるだろう」と指摘している。
一方、罪刑均衡の観点から死刑そのものの残虐刑該当性の判断はされていないが、後義輝 (1993) は「最高裁は『瞬間的に致命傷が加えられ、瞬間的に決定的な意識剥奪が行われて確実な死が速やかに招来されるに至ったことは、死刑の進化・人道化である』としているが、こうした見解こそ『死刑における受刑者の生命剥奪およびそれと不可分一体の精神的苦痛、その経験の残虐性』というものへの恐るべき無知・独断を示している。死刑の残虐性の中枢は生命剥奪、およびそれと不可分一体をなす精神的苦痛という点にあり、その精神的苦痛の原因・根拠は『確実な死が絶対的に強制される』という点にある。生命剥奪そのものが残虐である限り、最高裁が考えている『残虐でない死刑執行方法』などそもそも存在しない」と指摘している。
また、大法廷判決後の同年11月12日に極東国際軍事裁判で東條英機らA級戦犯7名が死刑判決を受け、12月23日に巣鴨プリズンで絞首刑となっているため、「当時日本を占領・統治していたGHQが、まさに日本の元戦争指導者達を死刑にしようとしていた手前、死刑制度を違憲とすることはできなかった」との指摘もある。
脚注
注釈
出典
参考文献
本事件の刑事裁判の判決文
- 広島高等裁判所判決 1947年(昭和22年)8月25日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第2巻3号199頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例ID:24000076(下記「27760012」の控訴審)、、『尊属殺、殺人、死体遺棄被告事件』。
- 判決主文:被告人を死刑に処する。訴訟費用は全部被告人の負担とする(被告人は上告)
- 最高裁判所大法廷判決 1948年(昭和23年)3月12日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第2巻3号191頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例ID:27760012、昭和22年(れ)第119号、『尊属殺、殺人、死体遺棄被告事件』「1. 死刑の合憲性 / 2. 被告人に精神病の懸念があることの主張と刑訴法第三六〇條第二項」、“1. 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない。補充意見がある。 / 2. 原審辯護人が原審公判において、被告人に精神病の懸念があることを主張したに過ぎないときは、刑事訴訟法第三六〇條第二項に規定する事由があることを主張したものとは解せられないので、原判決がその點について判断を示さなかつたからとて判断を遺脱したものとはならない。”。
- 最高裁判所裁判官:塚崎直義(裁判長)・長谷川太一郎・霜山精一・井上登・真野毅・庄野理一・島保・齋藤悠輔・岩松三郎・河村又介・藤田八郎(藤田は出張中のため署名押印できず)
- 全員一致(島・藤田・岩松・河村の4裁判官による補充意見+井上の意見あり)
- 判決主文:本件上告を棄却する。
- 検察官:橋本乾三
- 弁護人:西村真人
- https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/056385_hanrei.pdf (PDF)
- 「昭和23年3月12日判決 昭和22年(れ)第119号 本籍並住居 広島県佐伯郡吉和村字妙音寺原二千二百二十八番地 日雇稼 M 昭和二年一月十日生」『最高裁判所裁判集 刑事 昭和22年11月-昭和23年4月』第1号、最高裁判所事務総局、1948年、469-476頁、doi:10.11501/1363896、NDLJP:1363896/246、2020年12月28日閲覧。 - 1958年(昭和33年)12月発行。「国立国会図書館デジタルコレクション」にて閲覧可能(同文献のコマ番号246 - 249が該当ページ)。
- 最高裁判所裁判官:塚崎直義(裁判長)・長谷川太一郎・霜山精一・井上登・真野毅・庄野理一・島保・齋藤悠輔・岩松三郎・河村又介・藤田八郎(藤田は出張中のため署名押印できず)
関連する刑事裁判の資料
- 「付録 死刑事件判決総索引」『刑事裁判資料』第227号、最高裁判所事務総局刑事局、1981年3月、135頁、NCID AN00336020。 - 朝日大学図書館分室、富山大学附属図書館、東北大学附属図書館に所蔵
- 「検察官の上告趣意:別表 犯時少年の事件に対し死刑の判決が確定した事例」『最高裁判所刑事判例集』第37巻第6号、最高裁判所判例調査会、1983年、659-689頁。
- 永山則夫連続射殺事件(被告人:永山則夫)の上告審判決[事件番号:昭和56年(あ)第1505号 / 1983年(昭和58年)7月8日・第二小法廷判決]。永山以前に戦後、死刑が確定した少年事件(少年死刑囚)の一覧表(事件および裁判の概要・被告人の年齢など)が掲載されている。本事件の加害者である少年Mに関しては同資料660頁に掲載されている[参考資料:『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第2巻3号191頁]。
- 最高裁判所第三小法廷判決 1993年(平成5年)9月21日 集刑 第262号421頁、昭和62年(あ)第562号、『強盗殺人、死体遺棄、殺人、詐欺被告事件』「死刑事件(保険金殺人事件)(補足意見がある)」。 - 名古屋保険金殺人事件の死刑囚(2001年に死刑執行)に対する上告審判決。
- 最高裁判所裁判官:園部逸夫(裁判長)・貞家克己・佐藤庄市郎・可部恒雄・大野正男(大野の補足意見がある)
- 判決主文:本件上告を棄却する。(第一審の死刑判決を支持した控訴審判決を支持し、同判決に対する被告人側の上告を棄却)
雑誌・書籍・論文
- 向江璋悦『死刑廃止論の研究』(初版発行(初版印刷日:1960年10月10日))法学書院、1960年10月20日、430-432頁。
- 村野薫『日本の死刑』(第1版第1刷発行)柘植書房、1990年11月25日。ISBN 978-4806802983。
- 後義輝(旧姓:羽藤義輝)「第四章 死刑における精神的苦痛の残虐性 八 最高裁判所の認識に対する批判」『死刑論の研究』(第1版第1刷発行)三一書房、1993年9月15日、78-91頁。ISBN 978-4380932410。
- 奥田博昭 著「死刑囚の死刑制度違憲裁判事件」、(編者)事件・犯罪研究会、村野薫 編『明治・大正・昭和・平成 事件・犯罪大事典』(初版発行)東京法経学院出版、2002年7月5日、309頁。ISBN 978-4808940034。
- (編集製作)明治大正昭和新聞研究会 編「『読売新聞』1950年3月27日朝刊三面「死刑 是か非か 執行を待つ62名 電気椅子悔んで死んだ発明者」(読売新聞東京本社)」『新聞集成 昭和編年史 三十年版II』(刊行(印刷:2006年8月28日))(発行所)新聞資料出版・(発行者)中尾順子、2006年9月9日、380-381頁。ISBN 978-4884102043。
- 櫻井悟史「死刑制度合憲判決の「時代と環境」 ─1948年の「残虐」観─」『犯罪社会学研究』第42巻、日本犯罪社会学会、2017年、91-105頁、doi:10.20621/jjscrim.42.0_91、ISSN 2424-1695。
- 中島宏(著)、長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿(編)「死刑と残虐な刑罰」『憲法判例百選II』第55巻第5号、有斐閣、2019年11月30日、254-255頁、ISBN 978-4641115460。 - 第246号(通巻)
関連項目
- 少年死刑囚
- 死刑存廃問題
- 日本における死刑
- 絞罪器械図式
- 絞首刑
Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 死刑制度合憲判決事件 by Wikipedia (Historical)
Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou