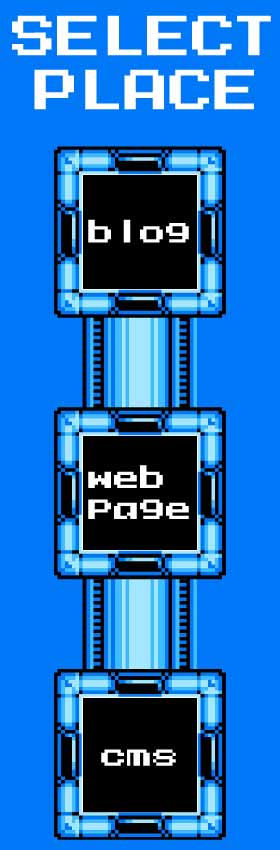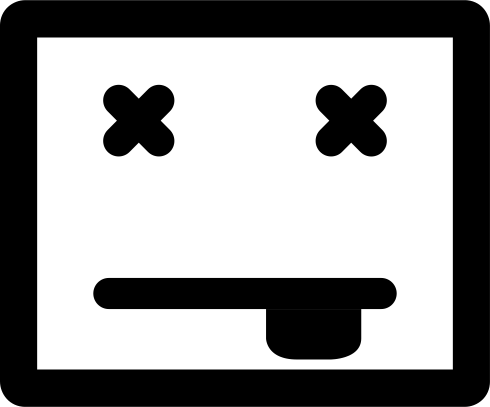
Search
マカイロドゥス亜科
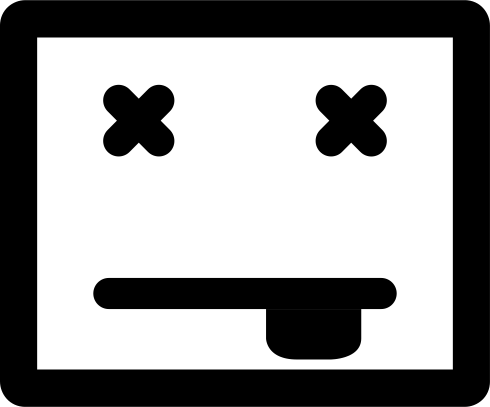
マカイロドゥス亜科 (Machairodontinae) は食肉目ネコ科(真のネコ類)に属する絶滅亜科である。アジア・アフリカ・北アメリカ・南アメリカ・ヨーロッパの各地で、中新世から更新世まで(2300万年前から1万1000年前まで)の地層から発見されている。
マカイロドゥス亜科には、有名なスミロドンをはじめとした「剣歯虎」としてよく知られる絶滅捕食動物が含まれているが、上顎犬歯の長さや大きさがあまり増大していない者も多く含まれている。時に同じように伸張した剣歯をもった他の肉食哺乳類も剣歯虎と呼ばれることがあるが、それらはネコ科には属していない。マカイロドゥス亜科の他に伸張した犬歯をもった捕食者には、ニムラブス科、バルボロフェリス科、肉歯目のオキシエナ科(特にマカエロイデス亜科)、後獣下綱のティラコスミルス科がいた。同様に長い犬歯を持っていたニムラブス科が中新世になってその数を減らした後、その生態的地位に置き換わるようにして繁栄した。
亜科の名称
"Machairodontinae" という亜科名は1872年にセオドア・ギル (Theodore Gill) によって名付けられた。模式属となるマカイロドゥス(Machairodus)は、μάχαιρα(machaira:短剣)οδούς(odous:歯)から、「短剣の歯」という意味を持つ。命名規約に従い Machairodus を属格化し亜科名用語尾の "-inae" をつけたものがこの亜科名である。ギルの書籍目録によれば1872年に哺乳類に関して発表した文献は"Arrangement of the Families of Mammals "であるが、当該文献中にてギルは "Machaerodontinae" という形でこの亜科を記している。
進化
ネコ科
マカイロドゥス亜科は前期または中期中新世のアフリカに起源がある。初期のネコ科動物であるPseudaelurus quadridentatus には犬歯の伸張化の傾向が現れており、マカイロドゥス亜科進化の基本となったと考えられている。本亜科に属する最初期の動物は中期中新世のミオマカイロドゥス (Miomachairodus) で、アフリカとトルコから化石が知られている。後期中新世までにマカイロドゥス類は同様に長い犬歯をもっていた古いタイプの食肉目であるバルボロフェリス科と多くの場所で共存していた。
伝統的にマカイロドゥス亜科には3つの異なる族が認められていた。すなわち、メガンテレオン (Megantereon) やスミロドン (Smilodon) を含む典型的なダーク型犬歯のスミロドン族、マカイロドゥス (Machairodus) やホモテリウム (Homotherium) を含むシミター型犬歯のマカイロドゥス族またはホモテリウム族、ディノフェリス (Dinofelis) やメタイルルス (Metailurus) といった属を含むメタイルルス族である。しかしながら最近メタイルルス族を現生ネコ類と同じネコ亜科に再分類される例が見られるようになってきた。最後のマカイロドゥス亜科の属であるスミロドンとホモテリウムは、1万年前、更新世の南北アメリカ大陸にもまだ生き残っていた。
「剣歯虎」は誤解を受けやすい名称である。マカイロドゥス亜科はトラと同じ亜科ですらなく、トラと同じような模様をもっていたという証拠もなく、この広い分類群の動物が皆現生のトラと同じ生態で生活や狩りをしていたのでないことは確かである。2005年に発表されたDNA解析では、マカイロドゥス亜科は今のネコ類の祖先と早い時期に分かれ、現生ネコ亜科との近縁性は低い、という分岐学的結論が出されている。
剣状の犬歯をもつ者は多くの場所で通常の円錐状犬歯をもつネコ類と共存していた。剣歯虎類はアフリカとユーラシアにおいて、前期または中期更新世まで、様々なヒョウ亜科動物やチーター類と競合していた。ホモテリウムは北ヨーロッパでは後期更新世まで生き残っていた。南北アメリカ大陸では、ピューマ・アメリカライオン・アメリカチーター・ジャガーなどと後期更新世まで共存していた。剣歯虎と円錐状剣歯ネコ類は、前者の最後の者が絶滅するまで食物資源に関して競合関係にあった。すべての現生ネコ類は大なり小なり円錐状の上顎犬歯をもっている。
進化史と表現型の起源
プロアイルルスとプセウダエルルスおよび現生ネコ類の3群を外群としたマカイロドゥス亜科の系統発生を各属の簡単な説明と共に示す。以下、Maは百万年前を表す。
分類
- ネコ科 Felidae
- マカイロドゥス亜科 Machairodontinae
- ホモテリウム族 Homotherini
- アンフィマカイロドゥス
- ロコトゥンジャイルルス
- ニムラヴィデス
- ホモテリウム
- メタイルルス族 Metailurini
- アデルファイルルス
- ディノフェリス
- ポントスミルス
- ステナイルルス
- メタイルルス
- スミロドン族 Smilodontini
- メガンテレオン
- パラマカイロドゥス
- リゾスミロドン
- スミロドン
- マカイロドゥス族 Machairodontini
- ヘミマカイロドゥス
- ミオマカイロドゥス
- マカイロドゥス
- ホモテリウム族 Homotherini
- マカイロドゥス亜科 Machairodontinae
Batallones-1 として知られる後期中新世の化石の宝庫の発見までは、スミロドン族とホモテリウム族の祖先の化石は数が少なく断片的な物しかなかった。そのため、剣状の犬歯の表現型の進化史、頭蓋下顎に影響を与える表現型、頚部・前肢の解剖学、などはほとんど知られていなかった。Batallones-1 の発掘以前は、高度に発達した剣状犬歯の表現型は多相遺伝的進化を経て急速に現れたという仮説が一般的だった。Batallones-1 からはスミロドン族の祖先である Promegantereon ogygia や、ホモテリウム族の祖先である Machairodus aphanistus の化石が出土し、彼らの進化史が解明された(ただし、スミロドン族の祖先は元々 Paramachairodus 属とされ、後に Promegantereon 属に再分類された)。ヒョウほどの大きさの P. ogygia (生息年代:9.0Ma)はスペインとおそらくその近辺に生存しており、その最もよく研究されている子孫でトラほどの大きさのスミロドン属は、1万年前の南北アメリカ大陸に生息していた。ライオンほどの大きさの M. aphanistus (生息年代:15.0Ma)はその最も研究されている子孫でライオンほどの大きさのホモテリウム属(生息年代:3.0-3.5Ma)と同じく、ユーラシアを闊歩していた。
剣状犬歯の表現型の進化についての現在の仮説は、Batallones-1 による知見を得て、この表現型はモザイク進化を経て徐々に現れてきた、という物になっている。正確な原因は不明なものの、近年の発見は獲物をすみやかに絶命させる必要性が進化の時を経てこの表現型を発達させるよう促す主要な進化圧だった、という仮説を支持している。破損した犬歯の発見例の高さが示すように、剣歯虎を取り巻く生物相環境は激烈な競争が際立つものだった。
破損した犬歯は、歯と骨との接触頻度が大きかったことを示している。歯・骨間接触の増加は、死体食の増加、迅速な獲物の摂食、過剰な攻撃性の増大、などの可能性が考えられ、これら3点全ては捕食者間の競争の激化により捕食機会が減少したことを指し示している。このような競争が激化した環境では捕食対象のより早い殺傷が求められる。なぜならば、もし獲物が(狩猟後の強奪などにより)摂食前に失われてしまえば、獲物を捕まえるために費やしたエネルギーコストは弁済されず、捕食者の一生の中でこのような事態がしばしば起こるようであれば、疲労・飢餓による死がもたらされるであろう。獲物をすみやかに殺傷できるよう改良された初期の適応は、P. ogygia と M. aphanistus の頭骨と下顎、P. ogygia の頸椎と前肢に見ることができる。彼らの化石により剣状犬歯の表現型進化における速度の重要性に対するさらなる形態学的証拠がもたらされている。
骨格
頭骨
マカイロドゥス類のグループでもっともよく研究されているのは頭骨、特にその歯である。多岐にわたる属・化石の保存状態の良さ・現生種との比較・グループ内の多様性の大きさ・生息していた生態系の理解などによって、マカイロドゥス亜科は、捕食者と被捕食者の関係・特殊化・強肉食性の分析の研究手法として最良の物の1つとなっている。
マカイロドゥス亜科は2つのタイプ、ダーク型犬歯グループとシミター型犬歯グループに分けられる。ダーク型犬歯グループは細く伸張した上顎犬歯を持ち、一般的にがっしりした体型をしている。シミター型犬歯グループは幅広く短い上顎犬歯と、おおむね小型の体と長い四肢を持っている。長い犬歯の者はしばしば伸びた骨質の鍔を下顎に持つことがある。しかしながら、2体のほぼ完全な化石のみが知られているゼノミルス (Xenosmilus) ではこの類型が破れ、ダーク型犬歯グループのようなずんぐりとした体躯と太い四肢と、シミター型犬歯グループのような幅広い犬歯の両方を持っている。
食肉目は植物や昆虫をかみ砕くことから肉を食べることに特化するに従ってその歯数を減少させていく。ネコ類の歯数はあらゆる食肉目グループの中で最少であり、マカイロドゥス類はさらにその数を減少させている例がある。ネコ科はその基本歯式として3/3・1/1・3/2・1/1という歯式を持つが、スミロドンのようないくつかの属では小臼歯が1本消失、または痕跡的になっている例が知られている。犬歯はなめらかに後方に曲がり、セレーション(鋸歯)が存在するが、加齢により減少していき、中年域(およそ4齢か5齢)になるとセレーションがほとんど消えてしまう。これらのような骨に残るヒントから、古生物学者は遙か昔に絶滅した動物において集団内の個体年齢を推定している。
長い犬歯を持つと大きく口を開く必要がある。ライオンの開口角度は95°であり、20 cm もの長さの犬歯を持つことはできない。その長さの犬歯だと上顎犬歯と下顎犬歯の間に数cm 以上の間隙を作ることができず、それでは獲物の殺傷に充分ではないからである。マカイロドゥス類は、収斂進化によって同様の犬歯を手に入れた他のグループと同じく、そのような犬歯を納めるために頭骨にいくつかの改良を加える必要があった。
哺乳類に於いて大きく口を開けるための主な障害は、顎の後方にある咬筋と側頭筋である。これらの筋肉は強力で広範囲に変異する咬合力に対応することができるが、その厚さ・部位・強さのためそれほどの柔軟性はない。より大きく口を開くため、この動物はその筋肉を小型化・形状変化させる必要があった。その最初の一歩は下顎骨筋突起の縮小である。咬筋、そして特に側頭筋はこの張り出した骨突起に付着するため、この突起の縮小は筋肉の縮小を意味する。筋肉が縮小すればするほどより大きな柔軟性の獲得とより大きな開口が可能となる。この観点における側頭筋の形状変化により筋肉の起始点・停止点間の距離は増大し、そのため筋肉はその伸張にふさわしい形態となるよう、より細長くなった。この変化により咬合力は弱くなっている。
マカイロドゥス類の頭骨においては側頭筋の形状に別の変化も示されている。口を開くときの主な制約は、開口時に側頭筋が顎関節の周りに過度に伸張されたならば断裂がおきてしまうということである。現生ネコ科動物では後頭骨が後方に伸び、その表面に付着している側頭筋は大きく口を開けたときには関節まわりに巻き込まれて伸ばされてしまう。側頭筋の伸張を軽減するために、マカイロドゥス類はより垂直な後頭骨を持つ頭骨を進化させた。イエネコの開口角度は80°、一方ライオンは91°である。スミロドンに於いては開口角度は128°となり、下顎底と後頭骨のなす角度は100°になっている。この角度は開口における大きな制限要素となっており、スミロドンに見られるように後頭骨と口蓋との角度を減少させると、開口角度はさらに大きくなる。後頭骨はまだ口蓋にまで伸びておらずまだ垂直にもなっていないので、開口角度は理論的には少し小さくおよそ113°あたりになるだろう。
マカイロドゥス類を含む多くの剣歯虎類の頭骨は上下に長く前後に短くなっている。頬骨弓は圧縮され、顔面の各部分は、目は高い位置にあり鼻先は短くなる、などの特徴を持つ。これらの変化は開口角の増大を補償するものである。マカイロドゥス類はまた、開口時の上顎犬歯先端と下顎犬歯先端の間隙を維持するために下顎犬歯が小型化している。
体骨格
スミロドンやメガンテレオンおよびパラマカイロドゥスなどのダーク型犬歯グループのマカイロドゥス類は、重厚さ・力強さで特徴付けられる。最も原始的なパラマカイロドゥスは派生的なスミロドンよりも小さくしなやかな体を持っており、進化において両者の間にいるメガロドンは体格においても中間型となっている。彼らは短い中足骨や重厚な体躯を持っていて、持久力のあるランナーではなかった。現生のライオンと比較すると、彼らの胸郭は前端が細く後端が広がった樽型をしている。肩胛骨は特にスミロドンでよく発達し、強力な肩の筋肉や三頭筋が付着するための広い面積を提供している。頸椎は非常に頑健で筋肉の付着点は頑強である。脊椎の腰椎部は短縮している。尾部は最も原始的なものから最も進化したものになるに従ってどんどん短くなり、その結果スミロドンではボブキャットのような尾になっている。体骨格だけを見た場合、彼らは現生ネコ類というより現生クマ類に似た構造を持っている。
マカイロドゥス、ミオマカイロドゥス、ホモテリウム、アデルファイルルス、ディノフェリス、メタイルルス、ポントスミルス、テライルルス、ロコトゥンジャイルルス、ゼノスミルスなどを含むシミター型犬歯グループはより多様性のあるグループで、ほとんどのマカイロドゥス亜科はこのあまり特殊化していないタイプに属する。この多数のメンバーを含むグループの犬歯は明らかに短く、概して幅広い。グループ内の多様性の大きさのために、典型例を提示するのは難しい。ホモテリウムはかつて蹠行性と考えられていたが、趾行性であることが判明した。このグループは一般的に平均より細身で小柄であるが、このグループのマカイロドゥスは全てのマカイロドゥス亜科の中で最大のもの(少なくとも最大のものの1つ)である。ダーク型犬歯グループとは異なり、大きな性的二形を示すものもいる。ホモテリウムは現生のブチハイエナによく似た傾斜した背中を持ち、同様に長距離の走行に卓越していたかもしれない。グループとしては長い四肢としなやかな体を持つのが普通だった。シミター型犬歯グループは平均的ダーク型犬歯グループよりも多くの歯が残っていた。 マカイロドゥスは跳躍の名手だったかもしれない。シミター型犬歯グループの頭骨以降の体骨格のみを見てみると、その形態は現生のヒョウ亜科動物(ヒョウ属とウンピョウ属)と比較的よく似たものとなっている。
解剖学的特徴と食性
咬合力
マカイロドゥス類の顎は、特にスミロドンやメガンテレオンのような長い犬歯を持った進化した種では、非常に弱い。コンピュータによる頭骨の復元をライオンとスミロドンにおいて行った結果、後者は暴れる獲物を保持しておくだけの圧力が不足していることが示された。主な問題点は顎によってもたらされる圧力である。すなわち、強い力をかけると顎の最も構造的に弱い部分で破断が起きる恐れが存在するのである。
スミロドンはその顎の筋肉のみを使ったならばライオンの1/3の咬合力しかなかっただろう。しかし、頭骨の後端に接続している頸の筋肉は強力で頭を押し下げさせることができた。顎が最大限に開かれる際には、顎の筋肉はもう有効に働くことはできない一方で、頸の筋肉は頭を下に押し下げさせ、その犬歯にいかなるものをも貫かせることができた。最大限に開いた口が閉じられる際には、顎の筋肉はそれをなんとかぎりぎりのところで行えた。
食性
良好な保存状態で化石化した捕食動物の骨には、生存時に捕食していた種に由来する判別可能なタンパク質が保存されていることがある。これらのタンパク質の安定同位体分析により、スミロドンは主にバイソン・ウマを捕食し、場合によって地上性オオナマケモノやマンモスを食べており、一方ホモテリウムはほとんどマンモスのみに依存していたことがわかった。
顔面
アメリカの古生物学者ジョージ・ミラー (George Miller) はマカイロドゥス亜科、特にスミロドンの軟組織におけるそれまで考慮されていなかった特徴を発表した。
彼の提唱したマカイロドゥス亜科の外観に関する変化の第1は、低い位置にある耳または高くなった矢状稜のために低くなったように見える耳である。この主張はその類を見ない特徴のために一般的には受け入れられてこなかった。他の現生の食肉類でこの理由により低くなった耳を持つものはおらず、Antón, García-Perea and Turner (1998) で指摘されているように、今生きている中で最も近縁な現生ネコ科動物では剣歯虎に比類すべき矢状稜を持った個体でも耳の位置はいつも同様である。復元の際の耳介の位置は、それぞれ復元する人物によって変化する。大きいか小さいか、尖っているか丸いか、高い位置か低い位置か、化石はこれらの特徴を保存しないので自由な解釈に任されていた。
ミラーの示した2つ目の点は、パグのような鼻面である。パグとその同類の犬種をのぞいて、現生の食肉類でパグのような鼻面を持っているものはいない。彼らの鼻先がパグのように比較的低位置にあるという事実はあまり認識されていなかった。ミラーの理論的推論はスミロドンの鼻骨が引き込まれていることをその根拠としている。ミラーの理論に対して、ライオンとトラの鼻骨の比較から批判が出されている。ライオンはトラと比較して大きく引き込まれた鼻骨を持っているが、ライオンの鼻鏡・外鼻孔はトラよりも引っ込んでるとは言えない。このように、ミラーによって提示されたスミロドンのパグのような鼻先は比較可能な動物間における物理的構造の証拠たり得ない。Antón, García-Perea and Turner (1998) によると、現生ネコ科動物の外鼻孔は鼻骨の長さとは関係なく皆同じような位置に開口し、それに照らし合わせるとスミロドンも現生種で観察されるのと同じ範囲に収まる。
3つ目の点は50%にもなる唇部の延長である。彼の指摘した他の点は多くの場合顧みられないのに対し、最後のこの点は現行の復元においてはっきりと描かれている。大きな開口角で獲物を咬む際に必要な柔軟性は、伸びた唇によってもたらされているのであるとミラーは論じた。この主張は科学界において反論を受けてはいるものの、芸術家からは指示を受けている。科学的な反論は、現生のネコ類(特に大型種)の唇部は信じられないほどの柔軟性を兼ね備えていて大きな角度の開口であっても通常の長さの唇で適切に伸張しているという点、現生の食肉目では唇のラインは常に咬筋の前に位置しており、その咬筋はスミロドンでは裂肉歯の直後に位置しているという点、を指摘している。それにもかかわらず、スミロドン・マカイロドゥスその他の種の復元においては大型犬の口元のような伸びた唇がしばしば見られる。
発声
スミロドンとライオンの舌骨の比較から、スミロドンひいては他のマカイロドゥス類も、現在の大型ネコ類と同じように吼えることができたと考えられている。
社会的行動
スミロドン
2009年に、南アフリカとタンザニアの保護区における社会性食肉目と単独性食肉目の比率を更新世の化石ベッドとして有名なラ・ブレア・タールピットの化石のそれと比較し、死にかけの獲物の録音した声にどのように反応するかを調べた研究が、スミロドンが社会性だったか単独性だったかを判断するために行われた。かつてラ・ブレア・タールピットは深いタールからなっており、そこに動物が捕らえられた。捕らえられた動物が死にかけているとき、彼らの鳴き声が肉食動物を惹きつけ、結果彼らもまた捕らえられた。ここは数多くの動物たちをタールによって捕らえ、保存してきた、北米で最も状態の良い更新世化石ベッドと考えられており、この研究による状況と似たものだったかもしれない。単独性の食肉目は他の捕食者と遭遇する危険性があるためそのような音の発生源には近づかないだろうというのが前提である。社会性の食肉目(例えばライオン)は恐れるべき他の捕食者がほとんどいないため、すぐにそのような呼び声に近づくだろう。この研究では、ラ・ブレア・タールピットで発見される動物の比率は後者の状況によく一致し、よってスミロドンはおそらく社会性だったとしている。
ホモテリウム
テキサス州のFriesenhahn Caveではおよそ400体分の若いマンモスの化石がホモテリウムの骨格とともに発見されている。ホモテリウムの仲間は若いマンモスを狩ることに特化して、開けた屋外で食べるのを避けて隔絶された洞穴に獲物を引きずり込んだのだと推測された。彼らはまた良好な夜間視覚を持っており、極地の夜間で狩りをするのが主な狩猟スタイルだったのだろうと考えられている。
アフリカ南部ボツワナで見られるライオンの亜種はトラに匹敵する体格を持つ。ボツワナのサブティ(Savute)では、30頭以上の個体で構成される群れがキリン・アフリカスイギュウ・ゾウなどの大型動物を専門に狩りを行う。襲撃の多くはゾウの視覚が制限される夜間に実行される。彼らはしばしば獲物を臀部から食べ始めるが、それは他のネコ類が行うやり方とは大きく異なる行動であり、獲物が死ぬ前から貪り始めることは頻繁に行われ、このような場合ゾウは失血死するまで生きたまま食べられる。子供や若年個体を対象とした狩猟から十分に成長した成体を成功裏に狩猟できるようになるまでの進展は比較的短期間で観察された。ボツワナのリニャンティ(Linyanti)にいる群れは専らカバを獲物とする。
現生のライオンがゾウの弱った成体や健康な若年個体を(しかも大量に)殺すことができるならば、ほぼ同サイズのホモテリウムも若いマンモスに対して同じようなことができたであろう。これは同位元素による分析からも支持される。しかしこの説は、この動物が(体格がネコ類中最大級のものの1つで社会性であったとしても)たとえ短い距離であっても400ポンドもの重さの獲物をみんなで力を合わせて「引きずって」くることがその歯を折らずに可能だったのか、という点から大きな反論を巻き起こした。後部に傾斜した背中と強力な腰椎はクマのような体格を示しているため重量物を引きずることは可能であったかもしれないが、犬歯を折らずに行うことは難しかったと考えられ、そして犬歯の破損はスミロドンやマカイロドゥスではよく見られるが、ホモテリウムではほとんど見られない。この件については、骨はスカベンジャーが洞窟に持ち込んだもので共産したホモテリウム化石とは無関係なのではないか、またこの動物が協力して獲物を引きずり込んだとしたらそれはどのようにしたのか、などの疑問点が残されている。
古病理学
マカイロドゥスは化石からは社会性であったことを示す証拠がほとんど得られていないが、彼らの犬歯は他の同類に比べて破損している割合が高く、そしてその後の広範囲な治癒の痕跡も見られる。Babiarz Institute of Paleontological Studiesに収蔵されている中国産のオスのMachairodus giganteus 化石は、破損後も使用されて摩耗した犬歯を持った老齢個体である。しかしながらこの個体は、社会性捕食者であったならば治療の機会があったであろう重篤な副鼻腔炎によって死亡しており、この事がこの化石の解釈にいくつかの異なる説をもたらしている。マカイロドゥスの幼獣において永久歯の犬歯の萌出には長い時間がかかり、それまでは完全に親の世話に依存する。ヒトにおいて無力な幼児を世話するという難事が、いくぶん未熟で発育不充分の状態で産まれるのに反して脳が大きく成長しなければならないという理由のために、部分的には単婚性と社会機構をもたらした原動力であると考えられている。他の種、特にゾウのように無力な仔をもつものでは防御のために群れを作るが、一方で大部分のクジラ類は群れを作らない。マカイロドゥスにとって群れを作ることは利点があると思われるが、母親が歯が萌出していない仔を3〜4歳になるまで単身で満足に養えたのかについて結論を出すのは難しい。
社会性を指示する他の古病理学の例としては、ラ・ブレア・タールピットから見つかった狩猟時に怪我をしているスミロドン化石の多さがある。狩猟の際の捻挫に起因する負傷に加えて、より重い怪我は社会性を強く示唆している。負傷者は怪我が治るまで長い間障害を持ったままであり、腫れ上がった足首を引きずるように歩き、何年も行動に制限があったと考えられている。ある例では骨盤を複雑骨折した若年個体が治癒した件が知られている。その個体は負傷した脚をほとんど使うことができず、他の3本の脚でのろのろと進むだけで、明らかに単独では狩猟ができなかった。もしも単独性の捕食者がそのような重傷を経て生き残れたのなら、それは非常に稀なことだったに違いない。何ヶ月も同じ場所から動けず、食べ物を持ってきてもらうか、仲間が倒した獲物のところまで這っていくことによってのみ生き延びたと考える方がずっとあり得る事だろう。
社会性仮説に対する反論
彼らが社会性だったかについてはいまだに議論が多い。スミロドンにおいて伝統的な単独性説を支持する証拠はその脳に見られる。ヒト、ハイイロオオカミ、ライオンなどほとんどの社会性捕食者は、同類の単独性捕食者よりもすこし大きい脳を持つ。スミロドンはむしろ比較的小さな脳を持ち、集団での狩猟のような複雑な協調行動はできなかったのではないかと示唆されている。タール・ピットにおいてスミロドン化石が多数発見されることは、同じくらい多く発見されるイヌワシが単独性であることから、社会性を示す証拠としては重要視されない。社会性であるハイイロオオカミやコヨーテもその地域に生息していたが、ピットで発見される彼らの化石は希である。
骨折の跡も社会性を示しているように見えるが、単独性の動物が重症から治癒する際の最もよい解釈は、彼らは充分な栄養をため込んでおり、必要に応じてそれを使うことができた、というものである。チーターはそれに対する反例のように見えるが、それは彼らが他のネコ類より華奢な体格を持つように特殊化した種だからである。ライオンやヒョウのようなもっと大きくてがっしりした体格のネコ類では、顎の骨折や筋肉の断裂のような重傷からでも回復した例がある。
犬歯の用途
マカイロドゥス亜科や他の剣歯虎型ネコ類の非常に長い犬歯の使い方については様々な説がだされている。
刺突
この説は犬歯を突き刺すのに使ったというものである。マカイロドゥス亜科は獲物に組み付き、口を開け、首を振りかぶって、獲物の皮膚と肉を貫くだけの力をこめて頭を振り下したのだろう。かつてこの剣歯虎の歯はヒトが手でナイフを扱うようなやり方で使用されたと考えられたこともあった。この犬歯は一見、脊椎を破壊したりグリプトドンのような動物の装甲を切り開くのにも使える、非常に有用で強力な道具のように見える。マカイロドゥス類を扱った初期の論文の多くは獲物をそのように殺していたとしている。それは一般にも広く受け入れられ、主要な説となり、絵画や映画でもそのように描かれた。
しかしながら、歯は金属ではなく支持のないエナメル質からできており、骨のような堅い素材に当たると簡単に折れてしまう。また、下顎が効果的な刺突の障害となってしまうということも議論された。これらの理由から、刺突説は科学界から否定されることとなった。
性的特徴
代わりの説として、この歯が本当に狩に用いられたのかという点が疑問視され、性選択のためではないかという議論が起こった。ライオンのたてがみのようないくつかの特徴は、オス同士の間の競争と、メスが独自の判断基準にもとづいて潜在的で健康な候補から配偶相手を選ぶことにより進化してきた。それぞれの種でその判断基準がどう選ばれてきたのか、性的装飾をつけたオスをメスが好むようになったのか、それとも扱いや取り回しが面倒な付属品をつけたオスを好むようになったのか、はよくわかっていない。
マカイロドゥス類においてはこの長い犬歯への選択はシカの枝角やライオンのたてがみと同様のものだと考えることができ、マカイロドゥス類は(そしておそらく他の剣歯虎様動物も)求愛・性的ディスプレイ・社会的地位のために使われた特徴を性選択を通して進化させるよう促された。マカイロドゥス類はおそらく求愛というゲームために奇妙な特徴を進化させたグループの1つというだけで、彼らの犬歯には特に機能的な目的が他にあるわけではないのだろう。彼らの犬歯は充分に発達していたがどちらかといえば壊れやすく、顎の筋肉は強くはなかったので、実際の機能的な用途については明確でないように思える。
この説に対する重要な議論がいくつか行われている。性的魅力を強化するためだけにそのような機能性とは無縁の特徴を持つ種のほとんどは、一方の性だけ(普通はオス)にその特徴が現れる。マカイロドゥス類の種は全てオスメス両方がそのような犬歯を持ち、マカイロドゥスの例をただの些細な例外とすれば、体格も同じである。性的な特徴を高度に発展させてきたほとんどの種では、少なくとももう1つ身体的な差異が見られる。それらの種ではふつう、体格が異なる。オスのシカは枝角を持つだけでなく、通常はメスよりも体が大きい。オスのライオンはたてがみを持つだけでなく、メスよりも大きい。アメリカチョウゲンボウのオスは、つがいの相手であるメスよりも明るく輝く体色をしているだけでなく、メスよりも小さい。マカイロドゥス類のオスとメスは同じサイズをしている。これらの特徴を性的ディスプレイの目的だけに発達させてきたのなら、マカイロドゥス類は食事や一般的機能に非常に大きな障害があっただろう。この特徴に適応するためだけに頭骨の形態を大きく変え、他の歯が数や大きさにおいて調整され、上下顎が広がるようにする、という変化を、途方もなく非現実的であると捉えるものは多いだろう。
死肉食
ほとんどのマカイロドゥス類は死肉食だったとする考えもある。これはその犬歯の機能に重きをおかないので、しばしば性選択説と共に唱えられる。現生の食肉類の多くも程度の差こそあれ死肉食をする。鋭い嗅覚と聴覚は死体を探したりダイアウルフやArctodus のような他の捕食者から獲物を奪うのに役立ち、ほとんどのマカイロドゥス類のずんぐりした形態に見られるように速く走ることは必要とされない。
現生のネコ類も場合に応じて死肉食をする。ライオンは強健なハンターだが、機会があれば獲物を奪う。トラやピューマは獲物を埋め、数日後に食べるために戻ってくる。ネコ類はみな病気や怪我をしたものを殺すことを好み、病気で動けない動物と死んだ動物の間には微妙な境界線しかない。ラ・ブレア・タールピットのスミロドン骨格の豊富さもこの仮説を支持している。ピットに捕らえられて死にかけているか死んでしまった動物は、現生のチーターのような真の強肉食性動物にとっては食べ物とはみなされないだろう。この説は最も古くからあるものだが、いまでも有力だとみなされている。
この考えに対する反論は様々な点を根拠としている。その歯は完全に肉食性であり、雑食性のイヌやクマがするような植物性食物をすり潰すような動きはできない。裂肉歯は肉を効果的に剪断できるような形をしており、現生のブチハイエナのような骨を噛み砕くようにはなっていない。オス・メス両方ともそのような犬歯を持ち、頭骨には対応した適応が存在することから、マカイロドゥス類はある程度まで場合によって両方を使い分ける便宜主義者だったのだろう。
頸部への噛み付き仮説
もっと一般的で広く受け入れられてるのが、マカイロドゥス類は喉元を切り裂くように噛み付いて狩をしていたというものである。現代のネコ類が使っている手法は喉締めで、喉の上部に噛み付き、気管を圧迫することで獲物を窒息死させるものである。かれらの犬歯は皮膚に突き刺してずれないようにするのがその働きの大部分であり、獲物に対して重要なダメージはいっさい与えていない。対してマカイロドゥス類が現代の同類と同じ手法を使ったならば、大きなダメージを与えていただろう。
この手法の大きな欠点は、まき散らされた大量の血液の匂いが、別のマカイロドゥス類やダイアウルフのような近くにいる他の肉食動物に気づかれてしまうだろうという点である。捕食者同士はしばしば競合関係を形成し、そのなかでの優位性は、現代のアフリカにおいてライオンとブチハイエナの間に見られるように、ある種から別のある種へ移りゆく。そのような状況では小競り合いは稀ではない。これらの頂点捕食者間での力と優位性のバランスは社会的要因のために謎のままである。これらの闘争において数の強さは重要である。たとえば、ダイアウルフは小さな群れで行動していたと考えられており、個々ではマカイロドゥス類より下位の存在であっても、集団の力でマカイロドゥス類を獲物から追い払うことがことができた。
しかしながら、マカイロドゥス類はダイアウルフが倒した獲物をあさることもできたはずである。2頭の単独性のマカイロドゥス類同士間の関係にも、つつき順位と第1位優位個体がすぐさま形成されただろう。この不確実性のためにマカイロドゥス類の生態的地位についての大部分はいまだにわかっていない。以下のこの仮説のバリエーションはみな控えめで静かなものだったとしてこの動物の生態を描いている。
一般的な「咬撃と撤退」
繊細な頸部に関係する最初の仮説は、マカイロドゥス類は獲物を押さえつけて特に場所を選ばずに頸部に噛み付き、大きな裂傷を与えた後に引き下がって獲物が失血死するのを待っていたというものである。頸椎に当たってしまって歯が折れるのを避けるため頸の背部を咬んではいけないという制限があるが、深い咬傷は頸部のどこであっても死をもたらしただろう。
この一般的な咬撃は届くところならどこでも行えるし、多数の仲間が必要でもない。腹を裂く仮説に比べると、1匹のメガンテレオンでも犬歯を折る危険を冒さずに大型のシカひょっとしたらウマも殺すことができただろう。静かにしておくため体重をかけて押さえつけておく間、暴れる獲物の四肢を避けるために体の大部分を獲物に対して引き離しておく、という手法に対してこの咬撃法が選ばれるのはそのためである。重く強靱な体躯をもったほとんどのマカイロドゥス類によって採られた待ち伏せ・忍び寄り型の狩猟法に適した迅速な咬撃法だっただろう。単独のマカイロドゥス類にとっても、この方法で大型動物を傷つけたのち離れ、獲物が倒れるまで後をつける、といったことは可能だったであろう。
この「咬撃と撤退」仮説については、その血のにおいと暴れる獲物がその場に他の捕食者やスカベンジャーを惹きつけてしまう、といった点から批判が挙げられている。単独の捕食者が傷をつけ、解放し、後をつける、という考えにはさらに強い反論がある。ネコは腹を満たすまでは獲物から離れていくことは滅多にないし、それは他の捕食者に獲物を奪われる危険を冒すことにもなる。
「咬撃と圧迫」
動物がマカイロドゥス類によって咬まれたとき(この仮説では重要ではないので血管の配置は無視する)、犬歯は気管の裏側に差し込まれ、小臼歯が気管を取り巻くことになる。この説ではマカイロドゥス類は咬撃の後、獲物を弱らせ窒息させるために気管を圧迫したと主張している。喉部にある太い血管がついでに傷つけられたならば大量の出血が起こり獲物の死を早めただろう。
現生のネコ類と、そしておそらくプセウダエルルスやプロアイルルスをはじめとするネコ類全体の基幹的な属も、獲物にとどめを刺す方法として「喉締め」を使っている。窒息により恐慌を起こした獲物の発声は押さえられ、現生のチーターやヒョウもこの方法を使っている。犬歯による裂傷と吸気の不足が獲物を死に追いやる。
この方法は犬歯による裂傷の効果を最大限に利用してはいない。犬歯を傷の中に突き刺したままにしておくことは、体からの出血をせき止めることになり、獲物の発声を抑えておけるとしてもその分獲物は死ぬのが遅れる。この方法においては、祖先的なネコ類の短い円錐形の犬歯と比較した際、長い犬歯に明確な優位性はない。どちらかといえば、暴れる獲物の喉に犬歯を突き刺したままにして犬歯が折れる危険性は、たとえどれだけ気をつけていたとしても、存在しうる利点を上回るものであり、そのためこの方法はあまり現実性があるとはみなされていない。
注意深い「剪断咬撃」
他の説では、進化したマカイロドゥス類は高度に特殊化しており、獲物の喉にある4つの主要血管を一咬みで傷つける事ができる特別な幾何学的配置を持っていたとしている。この仮説では血管を傷つけるために咬む場所の注意深い位置決めが必要という点で「咬撃と圧迫」説と似たところがあるが、マカイロドゥス類が引き下がって獲物に非常に急速に失血死をもたらすためにはより正確さが要求される。
血まみれにはなるものの、この説は他の説に比べて獲物の殺害にかかる時間が最も短い。マカイロドゥス類の獲物となる種における解剖学上の差異のため、例えばウマを殺すのに必要な幾何学的配置はバイソンには役立たない。これは獲物となる動物に、属レベルさらには種レベルでの高度な単一性の専門化をもたらす。これは、獲物となる種の移動や絶滅によりその動物を餌とすることに特殊化していた捕食者が死にいたる、という点で彼らの絶滅の原因を説明できるかもしれない。
この高度な特殊化は喉を切り裂く「咬撃と撤退」説の行きすぎで不必要な類説に思われるが、マカイロドゥス類がそれぞれ単一の獲物を狩猟するように専門化していたという考えは(ただし彼らがその獲物「のみ」を狩猟していたとするのは誤認 であるが)、受け入れられるものだとみなされている。しかしながら、おそらくはこの種の咬撃に付随したであろう騒音や悶着についての問題については解決されていない。獲物を一頭完全に無力化して確保するためにはおそらく数個体の捕食者が必要だったであろう。
「腹部剪断」
1985年、アメリカの古生物学者 William Akersten は切り裂くように噛み付いていたという考えを示した。この殺害方法は今日のハイエナやイヌ科動物に見られるものと似ている。マカイロドゥス類の一群が獲物を捕らえ無力化し、押さえつけている間に群れの一員が腹腔に噛み付き、引き裂いて切り開く。
この技法が機能するためには特別な運動の継続が必要となる。最初に、獲物は完全に無力化されている必要があり、捕食側のマカイロドゥス類は他の個体が獲物を押さえつけているためには社会性でなければならない。殺害を担当する個体は最大限まで開口し、その下顎を獲物の腹部の皮膚に押しつける。下顎犬歯と下顎切歯が押しつけられたところに窪みができ、下顎が押し上げられるにつれて下顎前歯の上方にかすかにしわがよる。次に、上顎犬歯が皮膚に食い込み、頸の筋肉を使って頭部を押し下げられ、下顎が「上がる」代わりに頭骨が「下がる」こととなる。犬歯が皮膚を貫くとそのまま下がってゆき、開口角が約45°になると頭骨の下降に加えさらに下顎も上昇をはじめる。ほとんどのマカイロドゥス類の下顎前端にある小さな鍔は頭骨の下降を助けるのに役立ったのだろう。この動物の口が閉じられたとき、上下顎の間、犬歯の後方には分厚い皮膚片が挟まり、そして低背部と前半身の筋肉を使って後退し、獲物の腹腔を切り開いた。一旦この大きな裂け目が開くと、腸はむき出しとなり、動脈と静脈は引き裂かれた。出血する獲物は数分で死にいたったであろうし、繰り返される咬撃による衝撃と腹腔から引きちぎられる内臓によりその過程は加速した。
この方法によって社会性のマカイロドゥス類は獲物となる動物に大きな傷を負わせることができた。引き続き起こる大量の出血で血だらけになっただろうが、社会性グループであるならばその場に惹きつけられるほとんど全ての動物を追い払うことがことが可能だっただろう。その噛み方は特殊なものでなくともよく、獲物の死を早めるために繰り返すことができ、ブチハイエナのような数種の現生種の殺害法としてもすでに観察されている。喉の場合と比べても腹部の柔らかい組織によって犬歯が折れることはありそうもなく、頸部とは違って犬歯の動きが増幅されることは腹部においてはない。この腹部剪断仮説は非常に信頼できると一般的にみなされている。ラ・ブレア・タールピットではスミロドン犬歯の破損例は稀であり、このリスクの少ない方法がそれに貢献していたかもしれない。
しかし、剪断咬撃はマカイロドゥス類にとってはいくつかの理由から問題のあるものだったかもしれない。ほとんどの有蹄類は腹部と後半身周辺の感覚が鋭敏であり、多くの捕食動物は家畜牛と同類の動物を捕まえて制圧するのに頸部や前半身を操作する。獲物を地面に引き倒しその前脚と後脚のあいだに位置取りするとしたら、そのマカイロドゥス類は蹴りを受ける危険性が非常に大きくなる。その蹴りには簡単に歯を折り、顎を砕き、脚を折り、その捕食者を不具にするか殺すかできるだけの力がある。
他の何頭かで獲物を押さえつけている間に別の個体にとどめの咬撃を加えさせるというように社交性を持つことによってその問題は解決される。さらに、バイソンのような大型の有蹄類の腹部の差し渡しは大きすぎ、皮膚の張りは強すぎるので、一頭のマカイロドゥス類が皮膚を咥えたりましてや体からそれを引きちぎるなどということは不可能である。剪断咬撃に関する第3の観点はその犬歯はうまくいけば獲物の腹部に大きな穴を開けることができるが、失敗すれば2本の長い溝を作って皮を剥ぐだけになるかもしれないという点である。そのような傷は痛みと出血をもたらしはするだろうが、死ぬまでの出血にはいたらず、失血死せずに逃げて生き延びることができるかもしれない。
2004年にラ・ブレア・タールピットから産出したスミロドン (S. fatalis ) のCTスキャンから型を取ったアルミニウム製の上下顎を用いて、剪断咬撃を含むスミロドンが用いた可能性のあるいくつかの咬撃技術を家畜牛の死体において再現する実験が行われた。ウシの腹部は差し渡しが大きすぎたので犬歯は皮膚を貫けず、下顎が邪魔をして犬歯がウシの体からそらされてしまうということがわかった。一方でそのモデルは、現生ネコ類のように下顎を引き上げることができたが、それは頸の筋肉の助けを借りて頭骨を押し下げていたマカイロドゥス類はおそらく行っていなかった方法である。その実験手法や手順にミスがあったことが判明しさえすれば実験結果は無効となるので、この仮説は生き残るかもしれない。
出典
- Turner, Alan (1997). The Big Cats and their Fossil Relatives. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-10228-3
- Antón, M.; García-Perea, R.; Turner, A. (1998). "Reconstructed facial appearance of the sabretoothed felid Smilodon". Zoological Journal of the Linnean Society 124 (4)
関連文献
- Van Valkenburgh, B. (2007). “Deja vu: the evolution of feeding morphologies in the Carnivora”. Integrative and Comparative Biology 47 (1): 147–163. doi:10.1093/icb/icm016. http://icb.oxfordjournals.org/content/47/1/147.full. . Full analysis of convergent evolution of hypercarnivores
外部リンク
- Evolution of feliform saber-tooth skull shape, on Nimravid's Weblog
- Saber-tooth skull diagrams
- Diagrams by Maricio Anton. All graphite drawings belong to Anton, along with several other artists. The second to last drawing depicts the versatility of the general neck bite and include a comparison of Machairodus and Panthera leo in head and face.
Text submitted to CC-BY-SA license. Source: マカイロドゥス亜科 by Wikipedia (Historical)
Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou