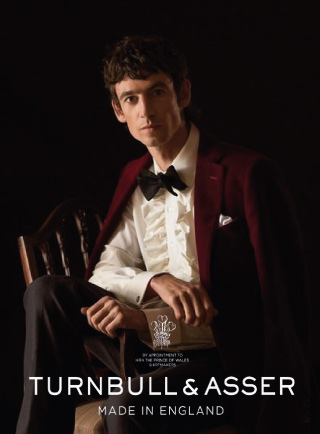Search
いるか座

主な天体
α・β・γ・δの4つの4等星で形作られる菱型のことを、欧米圏では旧約聖書のヨブ記の主人公にちなんで「ヨブの棺 (Job's Coffin) 」と呼ぶ。同じ星の並びを日本では「ヒシボシ(菱星)」と呼ぶ地方がある。
α星の固有名「スアロキン (Sualocin)」とβ星の固有名「ロタネブ (Rotanev)」は、1814年にパレルモ天文台台長のジュゼッペ・ピアッツィが刊行した星表『パレルモ星表』の第2版で初めて使われた。これは『パレルモ星表』の編纂作業を指揮していた助手のニコロ・カチャトーレが自分の名前をラテン語化した Nicolaus Venator を逆から読んだものをそれぞれの固有名としたものである。
恒星
2023年11月現在、国際天文学連合 (IAU) によって5個の恒星に固有名が認証されている。
- α星:太陽系から約238 光年の距離にある、見かけの明るさ3.800 等、スペクトル型 B9IV の4等星で三重連星。主星のAa星に「スアロキン(Sualocin)」という固有名が付けられている。
- β星:見かけの明るさ3.63 等、スペクトル型 F5IV の4等星で、分光連星。いるか座で最も明るく見える。主星のA星に「ロタネブ(Rotanev)」という固有名が付けられている。
- ε星:太陽系から約366 光年の距離にある、見かけの明るさ4.03 等、スペクトル型 B6IV の4等星。「アルドゥルフィン(Aldulfin)」という固有名を持つ。
- 18番星:太陽系から約245 光年の距離にある、見かけの明るさ5.506 等、スペクトル型 G6III の黄色巨星で、6等星。2008年に太陽系外惑星が発見され、2015年に主星の恒星には「ムジカ(Musica)」、惑星には「アリオン (Arion)」という固有名が付けられた。
- HAT-P-23:太陽系から約1,192 光年の距離にある、見かけの明るさ11.94 等、スペクトル型 G0 の恒星で、12等星。IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でパレスチナ国に命名権が与えられ、主星は Moriah、太陽系外惑星は Jebus と命名された。
その他に以下の恒星が知られている。
- γ星:太陽系から約116-117 光年の距離にある連星系。見かけの明るさ4.96 等、スペクトル型 F8V のγ1と、見かけの明るさ4.25 等、スペクトル型 K1IV のγ2からなる。
- δ星:太陽系から約221 光年の距離にある、見かけの明るさ4.417 等、スペクトル型 kA7hF1VmF1pSrEuCr の4等星。変光星としては脈動変光星の分類の1つ「たて座デルタ型変光星」に分類されており、4.38 等から4.49 等の範囲で明るさを変化させている。分光連星で、2018年の研究では1.78±0.07 M☉(太陽質量)の主星Aと1.62±0.07 M☉の伴星Bから成るとされている。
- R星:太陽系から約2,580 光年の距離にあるミラ型変光星。285.07日の周期で見かけの明るさを7.6 等から13.8 等の範囲で変化させる。
- わし座ρ星:見かけの明るさ4.946等の5等星。いるか座との境界近くに位置するわし座の恒星だったが、その非常に大きな固有運動により1992年頃に境界線を越境しているか座の領域に入った。これは、IAUにより星座の境界が確定した1930年以降、バイエル符号を付された恒星が越境した初めての例となった。
星団・星雲・銀河
いわゆる「メシエ天体」は1つもないが、2つの球状星団がパトリック・ムーアがアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ「コールドウェルカタログ」に選ばれている。
- NGC 7006:太陽系から約13万4300 光年の距離にある球状星団。コールドウェルカタログの42番に選ばれている。1784年8月21日にイギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルが発見した。
- NGC 6934:太陽系から約5万900 光年の距離にある球状星団。コールドウェルカタログの47番に選ばれている。1785年9月24日にウィリアム・ハーシェルが発見した。
- NGC 6891:太陽系から約8,400 光年の距離にある惑星状星雲。星雲内に二重の構造があり、星雲の拡大速度から内側は約4,800年前、外側は約2万8000年前に放出されたものと推定されている。
- NGC 6956:天の川銀河から約2億1400万 光年の距離にある棒渦巻銀河。宇宙の距離梯子として用いられるセファイド変光星とIa型超新星の両方が見つかっていることから、ハッブル定数を算定する研究材料とされている。
- ZW II 96:二つの銀河が衝突中の相互作用銀河。
流星群
いるか座の名前を冠した流星群で、IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされているものはない。
由来と歴史
紀元前3世紀半ばにマケドニアで活動した詩人アラートスの教訓詩『ファイノメナ (希: Φαινόμενα, 羅: Phaenomena)』では、α・β・γ・δの4星が成す四角形を「4個の珠玉」と称えている。帝政ローマ期の2世紀頃のクラウディオス・プトレマイオスの天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース (古希: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας)』、いわゆる『アルマゲスト』の中で、プトレマイオスが選んだ48個の星座の1つとされた。いるか座に属する星の数は、紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースの天文書『カタステリスモイ (古希: Καταστερισμοί)』や1世紀初頭の古代ローマの著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』では9個、プトレマイオスの『アルマゲスト』では10個とされた。
19世紀イギリスの天文学者リチャード・アンソニー・プロクターは、星座名を簡略化するために Delphinus から Delphin に変更することを提唱したが、世に受け入れられることはなかった。
1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Delphinus、略称はDelと正式に定められた。
中国
中国の天文では、いるか座の星々は二十八宿の北方玄武七宿の第三宿「女宿」に配されていた。ε・η・θ・ι・κの5星は、熟れ過ぎて腐った瓜を表す星官「敗瓜」を成した。これとは対照的に、α・γ・δ・β・ζの5星は、良い瓜を表す星官「瓠瓜」を成した。
日本
日本では、江戸後期の畑維竜(鶴山)の随筆『四方の硯』に
と記されており、「ひしぼし」という呼び名が使われていたことをうかがい知れる。
神話
紀元前3世紀頃の学者エラトステネースは著書『カタステリスモイ』の中で、ポセイドーンの妻になることを拒んで逃げたアムピトリーテーを探し出して連れ戻ったイルカを記念したもの、としている。
紀元前1世紀頃の著作家ヒュギーヌスやオウィディウスは、紀元前7世紀頃の詩人アリオンにまつわる話を伝えている。アリオンがシチリア島や南イタリアの音楽会から故郷に帰る際、彼の持つ報酬に目がくらんだ船員がアリオンを殺害しようとした。アリオンは死ぬ前に琴を弾かせて欲しいと願い、船員たちはこれを許した。アリオンが弾き始めると、どこからともなくイルカの群れがやってきて、曲を鑑賞した。アリオンが身を投げると、イルカがその背にアリオンを乗せて故郷に連れ帰った。イルカはその功績が称えられ星座になったとされる。
またヒュギーヌスは、アグラオステネースの『ナクソス誌 (Naxica)』で語られた話として、以下のディオニューソスにまつわる話を伝えている。ディオニューソスがまだ幼かった頃、ティレニア人の船頭たちは彼をナクソス島に連れて行き、そこでニュンペーたちに託した。船頭たちは船で立ち去ろうとしたが、それを察したディオニューソスはニュンペーたちに歌を歌わせて彼らを魅了させた。船頭たちは踊り、飛び跳ね、知らず知らずのうちに海に身を投げて、そこでイルカに姿を変えられてしまった。ディオニューソスは彼らのことを人の記憶に留めるため、イルカの姿を星々の間に置いた。
呼称と方言
世界で共通して使用されるラテン語の学名は Delphinus、日本語の学術用語としては「いるか」とそれぞれ正式に定められている。
明治初期の1874年(明治7年)に文部省より出版された関藤成緒の天文書『星学捷径』では「デルビニュス」という読みと「
現代の中国でも、海豚座と呼ばれている。
方言
日本では、α・β・γ・δの4星を「ヒシボシ」と呼ぶ伝承が、静岡・長野・奈良・和歌山・広島・大分・熊本に伝わっていた。また、これが転訛したとされる「ヘシボシ」が奈良県宇陀郡大宇陀町上片岡(現・宇陀市)や兵庫県神崎郡に、「シシボシ」が奈良県山辺郡丹波市町(現・天理市)に伝わっていた。
α・β・γ・δが作る菱形を生活道具等に見立てる例も見られる。たとえば、納豆を入れる藁苞に見立てた「ツトボシ(苞星)」という呼び名が静岡県榛原郡白羽村(現・御前崎市)、小笠郡日坂村(現・掛川市)、愛知県知多郡日間賀島村(現・南知多町)に伝わっていた。また、これを織物を織るときの道具である「梭」に見立てた「ヒボシ(梭星)」という呼び名が熊本県上益城郡甲佐町に、「ヒノホシサン(梭の星さん)」という呼び名が徳島県鳴門市に伝わっていた。
脚注
出典
参考文献
- 伊世同 (1981-04) (中国語). 中西对照恒星图表 : 1950.0. 北京: 科学出版社. NCID BA77343284
- 文部省 編『学術用語集:天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日。ISBN 4-8181-9404-2。
Text submitted to CC-BY-SA license. Source: いるか座 by Wikipedia (Historical)
Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou