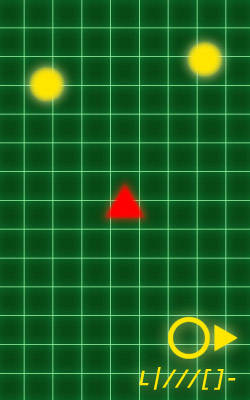Search
ミシャグジ

ミシャグジさまとは、中部地方を中心に関東・近畿地方の一部に広がる民間信仰(ミシャグジさま信仰)で祀られる神(精霊)である。長野県にある諏訪地域はその震源地とされており、実際には諏訪大社の信仰(諏訪信仰)に関わっていると考えられる。全国各地にある霊石を神体として祀る石神信仰や、塞の神・道祖神信仰と関連があるとも考えられる。
呼称
「ミシャグジ」の発音は「サク」「シャグ」「サグ」「サコ」「サゴ」「ショゴ」などが見られ、中には「おシャモジ様」まであるという。「ミシャグジ」のほかに、「ミシャグチ」「サグジ」「ミサクジ」「ミサグチ」「シャクジン」「シュクジン」「シュクジ」「シュクシ」「シキジン」「シキジ」「(お)さんぐうじ」「(お)しゃごじ」「じょぐさん」「しゃごっつぁん」「しゃごったん」など多様な音転呼称がある。
当て字と漢字の組み合わせも大変多く(200以上もあるといわれている)、諏訪では「御左口神」「御社宮神」「御射宮司」「御社宮司」「御作神」が見られるが、柳田國男は「石神」として取り上げたこともある。柳田の『石神問答』(1910年)には「石護神」「石神井」「宿神」などもある。金春禅竹の『明宿集』(1465年頃)は、「宿神」と「翁」とを同一存在と見なし、翁(宿神)を諏訪明神や筑波山の岩石などと同一視している。なお、石神(シャクジ)と石神(いしがみ)を同一視する辞書は複数あるが、『日本民俗大辞典〈上〉あ〜そ』は「石神(いしがみ)とは異なる」としている。また検地の神といって「尺神(しゃくじん)」をあて、検地棒や検地縄を奉納する所もある。このほか、「守護神」「佐軍神」「射軍神」「赤口神」「参宮神」「社子神」「曲口」「佐口」「山護神」「釈護子」「御佐久知神」「御闢地神」などとも表記される。
名前の由来については諸説あり、稲を守護することから「作(さく)神」とする説や、土地を開拓する(=さく)ことによってその中に秘められた生命力を表出させることから「御作(咲)霊(みさくち)」とする説、または蛇神とされたことから「御赤蛇」とする説などが唱えられる。
概要
ミシャグジさまの実態については様々な説があげられているが、解明されたとは言い難い。
分布・根源
ミシャグジさまの分布を調べた今井野菊によると、長野県には750余りのミシャグジ神社が存在し、そのうち諏訪109社、上伊那105社、下伊那36社、小県104社などが多い郡であるという。全国では山梨県160社、静岡県233社、愛知県229社、三重県140社、岐阜県116社、滋賀県228社のほか関東各県にも見られる。なお、大和岩雄(1990年)は今井が「ミシャグジ神社」とした滋賀県内にある神社のほとんどが大将軍神社であると指摘し、それはミシャグジさま信仰に含まれないとしている。また、群馬・埼玉・山梨ではチカト信仰と重なっている。
信仰の分布からミシャグジさま信仰の淵源は、諏訪信仰に関わるとする見方がある。昭和9年(1934年)に書かれた「地名と歴史」の中で柳田國男はこう書いている。
なお、近年では全国に見られる「ミシャグジさま的なもの」やミシャグジさまめいた石神はすべて諏訪に由来すると考えるのは乱暴で、諏訪大社において特化したミシャグジさま信仰と、諏訪から切り離されてしまった諏訪由来と思われるミシャグジさま信仰、または他所に見られる「ミシャグジさま的信仰」をそれぞれ分けて考えるべきである、という意見が現れている。かつての諏訪大社においてはミシャグジさまは特定の神官しか扱えない存在とされており、この神官が直接参向していなかった関東・東海等の石神信仰はそもそも諏訪地方のミシャグジさまとは直接の関係は持っていないはず、という指摘もある。
ミシャグジさまの実態
石の神か木の神か
幕末に書かれた『諏訪旧蹟誌』はミシャグジさまについてこう述べている。
『駿河新風土記』にも、村の量地の後に間竿を埋めた上でこの神を祀る一説がみられる他、『和漢三才図会』は「志也具之宮(しやぐのみや)」を道祖神(塞の神の一種)としている。
柳田國男は、日本にみられる各種の石神についての山中笑らとの書簡のやりとりを『石神問答』として1910年に出していた。神体が石ということからミシャグジさまを石神とする山中に対し、柳田は石を祀らないミシャグジさまもあり、石を祀ってもミシャグジさまといわない例があると指摘し、検地に使われる間竿がその神体として祀られることもあるから、ミシャグジさまは土地丈量の神であると主張した。また、ミシャグジさまは大和民族に対する先住民によって祀られていた塞の神(境界の神)で、大和民族と先住民がそれぞれの居住地に立てた一種の標識であるとも考察した。『石神問答』の再刊の序では、柳田は「是は木の神であったことが先ず明らかになり、もう此部分だけは決定したと言い得る」と宣言している。
この柳田の説に対して大和岩雄(1990年)は、自説に不都合だからか、柳田が『諏訪旧蹟誌』を引用した際に「此は即石神也」という文を省いていたと指摘し、そもそも『旧蹟誌』の著者がミシャグジさまを石神としたのは境の神に石神が多いからと書いている。さらに大和は、ミシャグジさまが祀られる古樹の根元に祠があり、神体として石棒が納められているのが典型的なミシャグジさまのあり方であるという今井野菊の観察に基づいて、ミシャグジさまはやはり石にもかかわっており、木の神と決定するわけにはいかないという見解を述べている。石埜三千穂(2017年)も、柳田が民間信仰としての石神の調査の延長としてミシャグジさまを扱っており、中世諏訪信仰にちゃんと注目していなかったからこの結論に至ってしまったと批判している。
鹿の胎児・酒の神
中山太郎は、1930年(昭和5年)「御左口神考」の中で口噛み酒を古くは「みさく」「さくち」と呼ばれていたことからミシャグジさまは酒神であるという説を立てた。更に鹿の胎児が「さご」と称されていたことや、諏訪大社と鹿の因縁深い関係からミシャグジさまの正体を雌鹿・孕み鹿とし、「鹿の胎児を造酒に用いる一種の呪術的作法が行われたのではあるまいかと思われるのである」と推察していた。
しかし、郷土史家の伊藤富雄にこの説に関して訊ねられた今井野菊は、鹿の胎児を酒造に用いる呪術的作法は聞いたこともない、と中山の推察を否定した。北村皆雄(1975年)も中山説を「どうも肯定しうるだけの説得力に欠けている」と批判すると同時に、中山が論考で取り上げた、三河国設楽郡振草村大字小林(現在の愛知県北設楽郡東栄町)で行われる種取りの神事で鹿の腹に納める苞が「鹿のサゴ(胎児)」と呼ばれるのをミシャグジさまの名称、または土地の開拓との関係を「なんらかの因縁をつけることができるかもしれない」と推測している。大和岩雄もこの情報を踏まえて、ミシャグジさまは植物(畑作・田作)だけでなく、動物にもかかわると提唱している。
ミシャグジさまと古木・石棒
藤森栄一・今井野菊・宮坂光昭・古部族研究会(野本三吉、北村皆雄、田中基の3人)らの研究により、ミシャグジさまと石棒や石皿との関係が明らかになった。上記の通り、今井の実地踏査で古木の根元に石棒を祀るのが最も典型的なミシャグジさまのあり方であることが判明した。このことから、ミシャグジさまは木に降りて、石に宿る神霊と信じられていたと考えられる。
北村は、ミシャグジさまの神体となっている石棒や石皿のほとんどが縄文中期のものであると指摘し、石棒は本来のミシャグジさまの神体ではなかったとする宮地直一の説に対して、ミシャグジさま信仰のルーツを縄文中期の地母神信仰に求め、石棒の中にその信仰的胚珠をもっていたと捉えた。いっぽう宮坂は神木・石棒信仰を古代の蛇信仰と結びつけ(神木-蛇-男根-石棒)、諏訪大社の龍蛇信仰はやはり縄文中期に遡るといわれるミシャグジさま(石棒)信仰と繋がっていると考えた。
ただし、諏訪大社上社の過去の祭事においては、ミシャグジさまが木や石だけでなく、笹や人間などにも憑くため、単なる木や石の神ではないという指摘もある。また、他の神(天白神、千鹿頭神など)を祀る社祠にも石棒が神体として納められることもある。この事から、石棒祭祀はミシャグジさま信仰特有のものではなく、それとは元々直接の関係がないとする見解もある。この説では「地中から出た特殊な石・石器(石棒や石剣など)を神社に奉納して祀る」という各地に見られる石神信仰が諏訪信仰の拡散につれてミシャグジさまと結びつけられたとされている。
その一例として、石埜穂高(2018年)は武蔵国(現・埼玉県、東京都)を中心に分布している氷川神社にも石棒・石剣を祀る例が多いことを挙げている。氷川信仰における霊石祭祀はミシャグジさま信仰と関連がなく、石棒・石剣を天叢雲剣に比定して生まれた信仰であるとしている。
神か精霊(力)か
現在はミシャグジさまを「神」として見るのが一般的であるが、細田貴助(2003年)は「精霊と人格神(神)とを、古くの日本人は区別していた。ミサクジさまを神とはしなかったであろう」と主張している。
これに対して石埜三千穂は、上社の神事においてミシャグジさまに憑かれた人が託宣する(神意を示す)ことがまずなく、1年の間に上社に奉仕する郷村を決める御占神事もあくまでも諏訪明神の託宣であって、祭事中に降ろされるミシャグジさまはそのために作用しているに過ぎないと指摘している。このことからミシャグジさまは本来、抽象的な「諏訪大神のために働く純粋な力」(すなわち自然エネルギーそのもの)と理解されていたという説を石埜が提唱している。北村皆雄と田中基(2018年)もミシャグジさまをマナ(実体性のない、人や物に付着する神秘的な力)や折口信夫の言う「外来魂」と例えている。寺田鎮子・鷲尾徹太(2010年)もミシャグジさまの本質を「生命力を励起するパワーのようなもの」、「空からやってくる(…)大気(空気・空)に充満するエネルギー」としている。
神徳
神徳は百日咳治癒、口中病治癒、安産、子育てなど様々だが、社祠・神座や伝承は年々消滅し続けている。
信仰
諏訪上社におけるミシャグジさま
守矢氏と神氏
諏訪大社は上社(かみしゃ)と下社(しもしゃ)という2つの神社で成り立っている。諏訪湖南岸に位置する上社にはかつて大祝(おおほうり)と呼ばれる最高位の神官と、そのもとに置かれた5人の神職が奉仕していた。諏訪氏(神氏)から出た上社の大祝は古くは祭神・建御名方神(諏訪明神)の生ける神体とされ、現人神として崇敬された。
その大祝を補佐して神事を司ったのは守矢氏出身の神長(かんのおさ、後に神長官(じんちょうかん)ともいう)である。神長は大祝の即位式を含め上社の神事の秘事を伝え、神事の際にミシャグジさまを降ろしたり上げたり、または依代となる人や物に憑けたりすることができる唯一の人物とされた。
諏訪地域に伝わる諏訪明神の入諏神話によると、建御名方神が諏訪に進入した際に地主神の洩矢神と相争った。洩矢神が戦いに負けて、建御名方神に仕える者となったという。守矢氏は洩矢神の後裔で、神氏は諏訪明神の後裔とされた。
地元の郷土史家はこの神話は諏訪に起こった祭政権の交代という史実を反映していると考えている。この説においては、外来の氏族(神氏)が諏訪盆地を統率した在地豪族(守矢氏)を制圧して、諏訪の新しい支配者となるが、守矢氏が祭祀を司る氏族として権力を維持した。この出来事が諏訪上社の祭祀体制の始まりとされている。この権力の交代劇の時期については諸説あり、諏訪に流入した神氏を稲作技術をもたらした出雲系民族(弥生人)とする説や、金刺氏(科野国造家、後に諏訪下社の大祝家)の分家、または大神氏の一派あるいは同族とする説がある。後者の場合、政権交代劇を下伊那地方に開花した馬具副葬古墳文化が諏訪地域に出現した時期(6世紀末~7世紀初頭)によく当てはめられる。
なお、入諏神話は中世に成立した説話で、考古学的知見と結びつけるべきではないとする見解もある。洩矢神が中世の文献では「守屋大臣」という名前で登場することから、入諏神話は中世に広く流布していた聖徳太子と物部守屋の争い(丁未の乱)にまつわる伝承の影響を受けている、あるいはその伝説をもとにして造作されたものという説が挙げられている。
ミシャグジさまと建御名方神
国史では諏訪の神が「建御名方神」という名前で登場しており、『古事記』や『先代旧事本紀』の国譲りの場面で建御雷神との力比べに敗れてしまう大国主神の次男として描かれている。しかし、『日本書紀』や、出雲地方の古文献である『出雲国風土記』と『出雲国造神賀詞』にはこの建御名方神が登場せず、『古事記』でも大国主神の子でありながらその系譜に名前がみられないため、建御名方神は国譲り神話に挿入されたという説を唱える研究者が多い。
諏訪にも建御名方神(正確に言うと『古事記』等における建御名方神)の影が薄いと言える。中世の祝詞には神名が出て来ず、「建御名方神」という神名もほぼ浸透しておらず、祭神の事を単に「諏訪明神」「諏訪大明神」「お明神様」等と呼ばれることが多い。また、『古事記』の説話とは異なる神話と伝承(入諏神話や、諏訪明神を蛇(龍)とする民話など)が現地に伝わっている。このことから、建御名方神は「ミシャグジさま信仰をヤマト王権の神統譜に組み入れた結果生まれた神名」(大和岩雄、1990年)または「朝廷への服従のしるしとして諏訪に押し付けられた表向けの神」(寺田鎮子・鷲尾徹太、2010年)で、諏訪の本来の神はむしろミシャグジさまであるという説が度々立てられている。
『日本書紀』の持統天皇5年(681年)8月の条には「使者を遣わして、龍田風神、信濃の須波(諏訪)・水内等の神を祭らしむ」とあり、諏訪に祀られている神は奈良時代以前に既に朝廷に風の神・水の神として崇敬されていたことが分かる。建御名方神を後世に創作された神とする研究者はこの「須波神」をミシャグジさままたは守矢神(洩矢神)としている。
なお、後で述べるように中世の上社ではミシャグジさま(御左口神・御社宮神)と諏訪明神は各々別神であると理解されていたことが明らかである。
ミシャグジさまと大祝
上社の大祝は神長が執り行う就任儀式(即位式)を受けていた。この際に、大祝となるべく選ばれた者(この職に若い男の子に当てる例が多い)は柊またはカエデの木のある鶏冠社(前宮境内にある上社摂社)の石の上に立ち、大祝の装束を着せられる。この儀式を受けることによって少年が諏訪明神の「御正体」(神体)となるとされた。実際には諏訪明神が8歳の男児に自分の衣を着せつけた後に「我に体なし、祝(ほうり)を以て体とす」という神勅を告げて祭神の身代わりとしたという伝承があり、それが神氏と大祝職の始まりとされている。
大祝に依り憑く神は実体のない霊的な存在とされることから、この神は建御名方神ではなくミシャグジさまであるとする見解がある。この説では大祝はいわばミシャグジの憑巫(よりまし)である。この説を唱えた田中基は「外来魂・ミサグジさまに装填したがゆえに大祝になった童児は、生き神様・現人神と考えられた」と述べ、春に行われる御頭祭で大祝の代理を務める6人の神使(おこう)にはミシャグジさまが付けられることを指摘し、「神使は構造上どう見ても仮の大祝であり、神使が御左口神であるならば、大祝は大御左口神であってタケミナカタではない」と論じた。なお、近年では意見を変えている様子である。
神仏習合
平安時代末期に諏訪に仏教が入り、上社本宮には神宮寺・如法院・蓮地院・法華寺ができた。本地垂迹説が広まると、上社の男神は普賢菩薩、下社の女神は千手観音の垂迹とされていた。室町時代に入ると、両部神道を学んだ神長・守矢満実が密教要素を導入して独特の「諏訪神道」を作ろうとした。天皇の即位灌頂や神道灌頂を参考にしつつ大祝を即位式を密教風にし、神事に密教的解釈を施した。
満実が著した奥義書『諏訪大明神神秘御本事大事』には両部神道・真言密教の影響が見られる。ミシャグジさまを「付け申す」時の儀礼には印相と真言が用いられていることはその一例である。
室町時代書写の『諏訪上社物忌令之事』(1237年成立)の写本(神長本)に載録されている「陬波六斉日精進之日記」においては、「諏方南宮法性大明神・十三所王子・御左口神」が礼拝の対象とされ、6つの斎日に六道の主として六観音と習合された御左口神(ミシャグジさま)が当てられている。
ミシャグジさまと諏訪御子神
近代の諏訪においては「御左口神」(御闢地神=土地開発の神)という名称は国土開発に功績のあったと言われる13柱の御子神を指すと解釈された。明治時代の神社明細帳では、諏訪に存在していたおよそ40のミシャグジ神社のほとんどが建御名方神(諏訪大神)の御子神を祀る神社として記録されており、その中には「健御名方命御子」として「御射宮司神」の名を挙げる神社が一社ある。長野県(旧信濃国)全体に見られる諏訪御子神を単独で主神として祀る神社を「社子神」「御佐久地」等と称される例もある。
ミシャグジさまを諏訪明神の眷属神・御子神として位置付ける見方は既に中世に見られる。例えば、守矢満実は「当社御神の王子」について以下のように述べている。
要するに、満実は御左口神(ミシャグジさま)を6人の神使(おこう)や「十三所(王子)」のように諏訪明神の王子神であると理解していた。これは、『上社物忌令』「陬波六斎日」に記されている「大明神・十三所王子・御左口神」と通じるとみられる。また、『守矢神長古書』には「当社にて御社宮神というのは皆御子孫の事言う也」とある。『諏方大明神画詞』(1356年)にも「十三所の王子」が諏訪明神を守護する眷属神として登場している。
石埜三千穂の説
石埜三千穂(2017年、2018年)は諏訪御子神(十三所王子)信仰の発展を中世の王子信仰に照らして自説を挙げており、それにはミシャグジさま(ここではミシャグジさまそのものと「ミシャグジさまを称する社祠」が区別されている)が絡んでいる。
元日の御占神事で1年の間に上社の神事に奉仕する郷村(御頭郷)が選定されると、選ばれた村から婚姻未犯の童男が神使(おこう)として出仕させられる。少年たちは新築されミシャグジさまを降ろした精進屋の中に30日間の精進潔斎に臨む。それが終わると神使(おこう)たちにミシャグジさまが付けられ、諏訪・上伊那の各地にある湛(たたえ・たたい)と呼ばれる聖地(樹木・岩石など)を巡る。精進屋に付けられたミシャグジさまが神上げされた後に取り壊され、その場に新たな祠が建てられる。これが「ミシャグジ神社」である。つまり、石埜の説では諏訪に見られる「ミシャグジ神社」は本来「ミシャグジさまを祀る社祠」ではなく「ミシャグジさまが降りた場所を記念する祠」である。
新造された「ミシャグジ神社」には諏訪明神の御子神(王子神)が祀られる。いわば、神長が降ろしたミシャグジさまによって新たな神が「生まれる」とされる。(上述の通り、石埜はミシャグジさまそのものを神長が扱う「諏訪明神のために働く力」・「生命力」という抽象的なものと解釈しており、神社に鎮座するような存在ではなかったとしている。)このことが諏訪御子神信仰の発展に繋がるとしている。
「前宮二十の御社宮神」
諏訪上社の
神原一帯は古くは祭事の中心地でもあったため、いうまでもなくミシャグジさまとの縁が深いと言える。嘉禎3年(1237年)の『諸神勧請段』に載録されている以下の神楽歌から、前宮には古くは「二十のミシャグジさま」が祀られていたという見解がある。
『諏訪大明神神秘御本事大事』にも「二十御左口神之王子」という呼称が見られる。
これに対して石埜三千穂は大祝の即位式の記録や古絵図をもとに前宮のミシャグジさま(前宮に付属しているミシャグジ神社)と前宮そのもの(前宮社・前宮大明神)はそれぞれ別の社祠であることを推測している。石埜の説では、前宮に本来祀られていたのは「ヒトとしての大祝一族の祖霊」であり、それと対比して内御霊殿(うちみたまでん、うちのみたまどの)に祀られているのは諏訪明神の幸魂と奇魂、すなわち「現人神としての大祝の神格」である。石埜は「二十の御社宮神」(=前宮を守護する御子神の社祠)を22柱の御子神を祀る若御子社に比定している。
鉄鐸(さなぎの鈴)
銅鐸によく似た鉄製の
「御宝鈴」「大鈴」「
鉄鐸の使用には礼銭が定められており、神長の収入源の一つであった。郡外不出のものとされ、宝鈴のタブーを犯すと契約が破綻するといわれていた。また、違約のある時はミシャグジさまの祟りがあると信じられていた。
天文4年(1535年)、武田信虎と諏訪頼満の和睦の際に、神長の守矢頼真が鉄鐸を鳴らしたという。
塩尻市にある小野神社にも12個1連の鉄鐸が保管されている。上社の鉄鐸とは異なり、原形のまま鉾に吊るされている。多数の麻幣が結びつけられており、御柱祭が行われる年に1かけずつ結ぶ習わしが現在も続いている。
ミシャグジさまの祟り
『諏方大明神画詞』(諏方祭巻第一 春上)は「御作神」(ミシャグジさま)について「若(も)し触穢ある時は、此の神必ずたたりをなす。鳥犬に至るまで其の罰を被る」と述べており、つまりミシャグジさまは穢れた者に祟りをなす神で、その祟りは一族、家に飼う犬鳥にまで下るという。郷土史家の宮坂光昭(1991年)は以下の出来事を「ミシャグジさまの祟りがあった」として挙げている。
- 現人神である大祝は諏訪郡を出てはならない、または穢れの元となる人や馬の血肉に触れてはならないという厳しい不文律があった。この掟を破って奥州征伐に従軍し、また源義家(八幡太郎義家)の誘いで上京しようとした諏訪為信の子為仲は、大祝在職中ということで諏訪社一同に反対されたものの、それを押し切って出立したが、社の鳥居を出ると馬が数匹病気で倒れ、更に群外を出ると馬が7匹も病死した。やがて美濃国にたどりついたところ、源義光一行と酒宴を催するが、部下双方が喧嘩し死傷者を出すに及んで、為仲は責任をとって自害する。父の為信はこの事件を神罰と見なし、遺児の為盛を大祝の職に就けさせなかった。次に大祝となった為仲の弟の為継(次男)は任職3日後に頓死し、同じく弟の為次(三男)も任職7日後に急死したため(いずれも神罰とされている)、四男の為貞が当職を継ぐことになった。(ただしこの出来事を記録する『画詞』や『前田本 神氏系図』では「神罰」という表現が見られるのみで、ミシャグジさまの仕業であると明記していない。)
- 大祝即位式の時、神長官における授職を行わない人には神罰が下るとされた。戦国大名諏訪頼満は嫡子の頼隆を大祝に立てたが、頼満は32歳で死去した。神長官の守矢頼真はこれを「即位式不足による御罰」と言っている。大祝となった頼隆の嫡男である諏訪頼重も即位式も正式でなかったためか、母が死亡したので大祝を退位した。ところが、次の大祝として立つべき人がなく、再度大祝となったものの、即位式もなく、かつ一周忌もたたずして大祝となった結果、やがて武田晴信(信玄)に滅ぼされる。
ミシャグジさまと上社の神事
諏訪上社においてミシャグジさまは諏訪明神を祭る祭礼には欠かせない役割をしてきたが、単独に祀られることはなかった。ミシャグジさまが主に活躍したのは、冬から春にかけて行われる神事祭礼であった。
御室神事
旧暦12月22日になると、諏訪郡の郷民が奉仕して神原(前宮)の一部に建築した
『諏方大明神画詞』(1356年成立)には以下のように書かれている。
『年代神事次第旧記』(室町初期成立)によると御室には柱4本、桁2本、梁2本がある。田中基の計算によると24畳分の菅畳が用意されたため、広さはそれ以上ということになる。中には「萩組の座」というものがあり、神長による祭事の覚え書きである『年代神事次第旧記』(室町初期成立)には御室本体の用材とは別に「東の角、南の角、棟木、東西の桁、囲い」とあることから、御室の中に設けられる仮小屋と考えられる。「うだつ」とも呼ばれるこの構造物には大祝、神長、神使(おこう)しか入ることができなかった。破風には葦で壁体を作り、そこにミシャグジさまを祀ったという記録もあるが、このあたりの記述が混乱しているため、これは御室自体の破風を指すのか、「萩組の座」の破風を指すのか不明である。ミシャグジさまの依り代も剣先板と呼ばれる板(後述)なのか、八ヶ岳西麓にある神野(こうや、禁足地とされた上社の神聖な狩り場)から切り出された笹なのか、それとも別のものなのかよくわからない。
22日の祭事の時に御室に入れられる「第一の御体」とは、祭事に関する部分が所々改変されている神長本『画詞』から、ミシャグジさまであることが明らかにされている。また「御体三所」は、『旧記』から「そそう神」と称する神霊(後述)で、23日の神事の項に「例式小へひ入」とあることから3つの蛇体であることが分かる。小蛇に麻と紙をからめて立てられるが、これは注連縄に紙をつけ、大幣に麻を垂らすのと同じで、蛇形に神格を付着するためである。
『旧記』によると、24日の夜(大巳祭)にはミシャグジさまを依り憑けた「御笹」が「萩組の座」の左より、「御正体」(上記の3体の小蛇)がその右より搬入される。「萩組の座」に安置された笹は「うだつの御左口神」とも呼ばれ、3月丑日までに御室の中に位置する。大小の蛇形も同様で、3月まで御室に納められていた。「萩組の座」の中で何が行われたのかははっきりしないが、大祝が笹を持ちながら唱え言をしたようである。
25日の大夜明祭にはハンノキの枝で出来た長さ5丈5尺(約16m)、太さ1尺5寸(70cm)の蛇体3体と「又折(またおり)」と呼ばれるものが御室に入れられる。「御身体」または「ムサテ」と呼ばれるこの蛇形も「そそう神」であるという。すなわち、大小の蛇体が各々3体ずつ2日間を隔てて入れられている。田中基はこれについて、小蛇が大蛇に急成長することで神霊であることを示した儀式的表現であると述べている。蛇形が御室の中に安置されるのは3月卯の日までである。
ソソウ神
御室神事関連の申し立て(祝詞)では「そそう神」という神が見られる。12月22日の神事と、23日の神事、25日の神事と二十番の舞、更にまた3月末日の神事の際に何度も繰り返される申し立てには、その出現の様が語られている。
「道」の「口・中・尻」に「そそう神」が現れ給うたので喜んで仕えるという内容の祝詞である。上社神域の北限である有賀(現・諏訪市豊田)にある「こしき原」、その次に真志野(現・諏訪市湖南)、そして大祝が住む館・神殿(ごうどの)の入り口付近にある所政社(所末戸社)がその出現の場所として特定されており、諏訪湖の方角から神原(前宮)まで水平に現れるという性質を持つと考えられる。
「そそう神」の正体については以下の説が挙げられている。
- 女性的精霊説
- 女性器は「そそ」とも呼ばれていることから、「そそう神」は諏訪湖の方より水平的に訪れる女性的精霊と解釈され、上空から降りてくるミシャグジさま(ここでは男性的精霊とされる)と対照的な存在とされている。この説では、御室の中に笹の付いたミシャグジさまと「そそう神」を象徴する蛇形が入れられるのはこの2つの精霊の「聖婚」を表し、それとともに参籠する大祝は蛇との婚姻で生まれる聖なる子供であると解釈される。12月25日に演じられた神楽歌(「総領申す」)がかなり淫猥な表現になっていることから、御室神事が性的な意味を持っていたと考えられる。
- 祖霊神(諏訪明神)説
- この説によると「そそう神」は「祖宗(そそう)神」、すなわち大祝の祖霊としての諏訪明神を指すのである。ここでは御室神事が他界(根の国)からやって来る龍蛇の姿を持った諏訪明神が御室に籠ることによって衰えた生命力(=ミシャグジさま)を増殖させることを意味すると解釈されている。また、これによれば冬の御神渡りは本来、龍蛇体の祖霊神の出現の証として見られたという。
宮地直一(1937年)はこれを諏訪明神を蛇体とする説のもととしていた。
蛙狩神事
元日の朝に上社本宮で行われる蛙狩神事では、本宮前の御手洗川から捕らえられたカエルが小弓と矢で射抜かれ、生贄とする。かつてはカエルを「射取る」のが神使(おこう)の役目であり、6匹を捕獲したのは6人の神使がいたからと思われる。しかし時代が下がるとカエルの数も少なくなり、現在は2匹が平均的である。「不闕の奇特」と言われるほど川には必ずカエルが現れると信じられ、これが諏訪大社七不思議の一つとして数えられている。射抜かれたカエルは本宮の「帝屋」(現在の勅使殿)に座す大祝の前に供えられ、丸焼きした後に神薬として配られた。
中世の伝承では諏訪明神による蝦蟆神の退治を模した神事とされているが、カエルを供える本当の理由は謎に包まれており、いろんな説が挙げられている。一説ではこの話が蛇神としての諏訪神と土地神(ミシャグジさまあるいは洩矢神)による神権争奪を意味するという。
御占神事
元日の夜、神長が御室の中で当番として1年間上社に奉仕する御頭郷と神使(おこう)を抽選する御頭御占神事(神使御頭御占、神使殿御頭定とも)を行う。
6人の神使と14人の村代神主(むらしろこうぬし、諏訪郡内の郷村を代表する在地領主層)のために神長は「二十のミシャグジさま」を降ろす。その神体は剣型の板(剣先板)で、これが藁馬に差し立てられ、御頭の役名(「内県介(うちあがたのすけ)」等)が書かれた紙を小刀で刺し止める。ミシャグジさまを降ろすと神長は大祝に対し呪文を唱えて、ススキの芯を投げ打っての丁半の占いで神使(内県介・宮付(みやつけ)、外県介・宮付、大県介・宮付)を選んだ。新しい神使が決定されると前年の神使は退下する。
今でも御頭郷を選ぶ占いは諏訪大社の宮司によって行われるが、諏訪頼水が1614年(慶長19年)に諏訪の郷村を15組に分けてから輪番制に替わったため、形ばかりの神事となっている。
神使の精進
御頭郷に当たった村には上社の神印が押された御符(みふ)が授けられ、村境に境締めの幣帛が立てられる。神長が神使(おこう)のために新造された精進屋(お贄場、御頭屋とも)にミシャグジさまを降ろし、神使とその従人、鹿人(ろくびと、料理人)等が2月上旬から30日間、この中に厳しい精進潔斎を行う。物忌みの期間中、女性との交接や触穢は禁じられている。もし違反する時は、ミシャグジさまの祟りがあると信じされていた。
精進初めの日には神長が鹿の皮を敷き、鹿の足を載せたまな板を置き、神使にミシャグジさまをつける儀式を行う。透き烏帽子・狩衣を着た神使たちは神長から「極意の大事」の印相と呪文を授けられる。心身を清浄に保つのが重要であるため、10日ごとには装束と、精進屋にある畳や調度品等がすべて取り替えられ、火も毎日3度改めた。行水は初めの10日間は1日1回、その次の10日間は1日2回、そして最後の10日間は1日3回を取った。そればかりでなく、『上社物忌令』では精進屋に入る前に「七日の精進」が定められている。御頭郷全体にも禁戒が定められ、諏訪社の社殿造営(現在の御柱祭)と同様に奉仕期間中は祝い事(元服・結婚など)や葬式が禁じられた。
精進屋の前に設置された鳥居型の御贄柱(おんね柱)に付いている25本の串には贄の鹿肉が大量に掛け並べていた。
境締めは今でも御頭郷となる地区の境に立てられている。御室や神使関連の神事のほとんどが廃止してしまったため、現存する諏訪大社の神事の中でミシャグジさまが登場するのはこれだけである。
精進期間が終わると神使が精進屋から出て、神長が「ミシャグジさま上げ」(神返し)をしてから精進屋は撤去される。神長は精進満行の証として神使の首に「結麻(ゆいま)」(結袈裟と似たものと思われる)を懸けて、また別に印相・真言を授与した。しかし神使の精進生活はこれで終わったわけではなく、江戸時代の記録では神長家の敷地(現在の神長官守矢史料館)にある潔斎屋に神長ともども7日間籠った。つまり精進屋に入る前に7日間、忌明けの最後に7日間潔斎をしたということになる。こうして忌み籠りの生活を終えた神使たちは大祝の身代わりにふさわしく聖化されたものとなる。
神使たちは本宮に参詣して、若芽のカワヤナギの幣を4束ずつ奉納してから、諏訪明神の御正体(大祝)の代理となったという旨の申し立てをする。
他所におけるミシャグジさま的信仰
ミシャグジさまと三狐神
三狐神はサグジ、シャグジ、シャゴジ、ミシャゴジ等と読まれる。三狐神(サグジ)は農家で祭る田の神(田畑の守り神)であり、「三狐神(さんこしん・さんこじん)」の音から変化した名称である。「三狐神」を「シャゴジ」と訓んで、シャグジの同類とする考えもある。機殿神社の末社では、諏訪の土俗神として「三狐神(ミシャゴジ)」が祀られている。また、伊勢市の二見興玉神社に存在する「天の岩屋」は、稲荷神(宇迦之御魂神)を祀る三宮神社の遺跡とされるが、かつては石神(シャグジ)または三狐神であり、洞の奥に燈火が点されていた。また東京都練馬区にある石神井神社(祭神 少彦名命)でも石剣(石神)が祀られおり諏訪大社におけるミシャグジさま信仰となんらかの形でつながっている可能性がある。また、当区の石神井川流域の遺跡には旧石器時代の遺跡もあり、かなり前より生活圏が成り立っていた可能性が高い。
注釈
出典
脚注
参照文献
Text submitted to CC-BY-SA license. Source: ミシャグジ by Wikipedia (Historical)
Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou